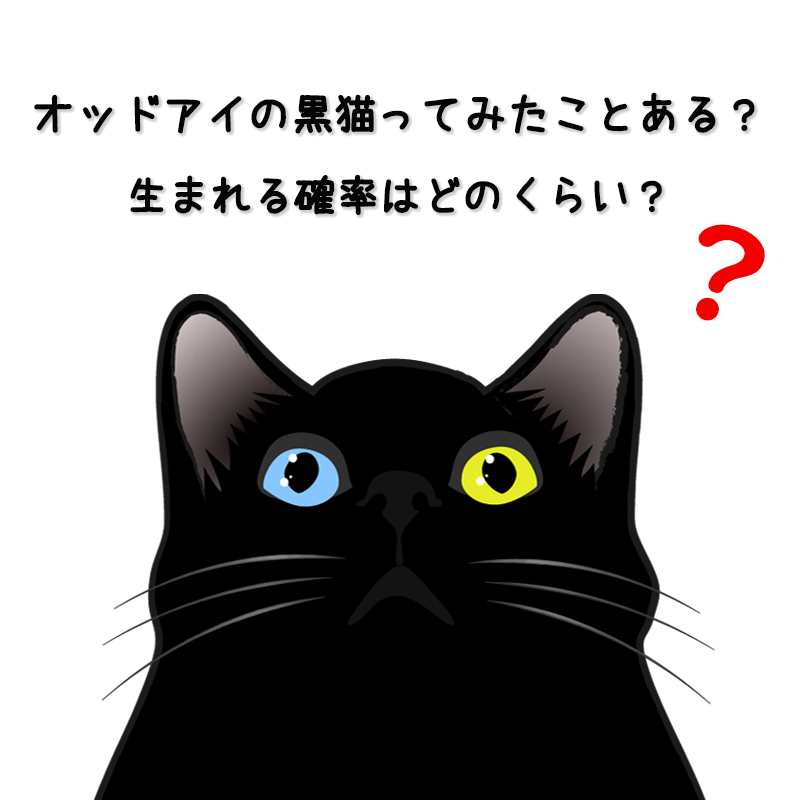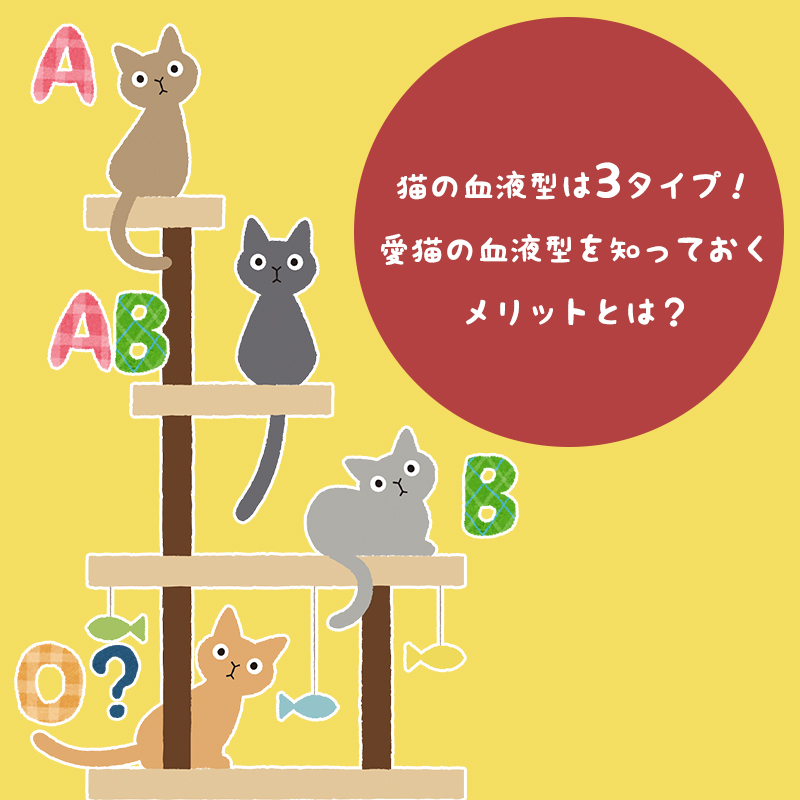1.オッドアイとは
3.白猫だけがオッドアイになる?
3-1.白色の猫にオッドアイが多いのはなぜ?
3-2.オッドアイの猫は短命?
3-3.オッドアイの猫が生まれてくる確率はどれくらい?
5.オッドアイになりやすい猫の種類
5-1.ターキッシュバン
5-2.ターキッシュアンゴラ
5-3.ジャパニーズボブテイル
5-4.メインクーン
オッドアイとは

オッドアイとは、左右の瞳の色が違う「虹彩異色症」こと。
「オッド」は、奇数・不揃い・片方の、を意味し、左右各々の瞳の虹彩色が異なっていることをいいます。虹彩異色症は、片方の瞳がキトンブルー(青色の瞳)、もう片方がイエロー、グリーン系であることが多いです。
オッドアイは稀に人間にもみられますが、人間よりも猫や犬に多いです。
その原因としては、先天的なものとして遺伝子の突然変異によって起こるのが一般的です。
一方で後天的な理由としては、子猫の時のキトンブルーの瞳は成長するとメラニン色素によ本来の色に変化しますが、片方の瞳だけそのまま青いまま成長してしまうケースがあります。その他、目の病気や老化によって虹彩の色が変化し、オッドアイに後天的になる場合もあります。
「幸運を運んでくる」と呼ばれるオッドアイの猫
オッドアイは「幸運を運んでくる猫」と呼ばれ、縁起が良いものとして親しまれて日本でも「金目銀目」と愛されています。タイでは「ダイヤモンドの瞳」とも呼ばれ、世界中の人々から親しまれている猫であり、青い瞳をした猫を大切にしているといいます。
白猫だけがオッドアイになる?
オッドアイになる猫は、特に白猫が多いといわれていますが、黒猫、キジトラ、サバトラなどの種類でもオッドアイが現れます。その中でも特に多くオッドアイになりやすい猫が「白色の猫」になります。
◆白色の猫にオッドアイが多いのはなぜ?
先天的な理由として、白い被毛を作り出す遺伝子のメカニズムが遺伝子異常を発生させることが原因とされています。
突然の遺伝子変異によって、色素を作る細胞「メラノサイト」の働きを抑制させてしまうので、メラニンが少なくなり、被毛と眼球にメラニンが行き渡らなくなるためといわれています。
また、白い被毛をつくり出している遺伝子が、ブルー系の瞳側の耳に聴覚障害を引き起こす可能性があるとされています。つまり、白い被毛をつくり出している遺伝子には被毛のメラノサイトがなく、それが瞳の細胞に影響を及ぼすことで、オッドアイと呼ばれる虹彩異色症を引き起こします。
◆オッドアイの猫は短命?
多くの場合、先天的な遺伝子異常が原因ですが、一般的な健康の猫と比べて体が弱く生まれてくることが多いです。
また、オッドアイだからといって、視覚に先天的な障害はほとんどありませんが、先述した通り、聴覚障害を持っている確率が高くなります。確率は30%~40%程度ともいわれています。
視覚に障害を持って生まれることはほとんどありませんが、虹彩の色が生まれつき薄いので、紫外線対策をして目に刺激を受けないように十分な対策をとる必要があります。
◆オッドアイの猫が生まれてくる確率はどれくらい?
生まれる確率は人間よりも猫のほうが高いといわれ、特に白猫の場合は約25%の確率で生まれてくるといわれています。4匹に1匹なので、結構高い確率でオッドアイが生まれることになります。
また、親となる猫が白猫である場合、その子供が聴覚障害を持って生まれてくる確率は52~96%だといわれています。このことからも白猫の場合、高確率で聴覚に何かしらの障害を持って生まれてくる可能性が高いです。
黒猫にもオッドアイは存在する?
白猫に比べると数は少なくなりますが、黒猫にも存在します。
オッドアイが生まれてくる確率はそもそも低いですが、その上ほとんどの場合が白猫から生まれてくるので、黒猫のオッドアイが生まれてくることは非常に珍しいです。
先述の通り、オッドアイは白い被毛をつくる遺伝子の異常によって色素細胞が作られず、虹彩の色が薄くなるので、先天的な理由で黒猫のオッドアイが生まれる確率はかなり低いと考えられます。
黒猫がオッドアイの場合は、主に後天的な原因です。
後天的になる場合は事故や緑内障などの目に異常が出ている場合もありますので、獣医師に相談しましょう。
オッドアイになりやすい猫の種類

オッドアイになる猫は白猫に多いことから、純血種の中ではターキッシュバン、ターキッシュアンゴラ、ジャパニーズボブテイルの3品種に比較的現れやすいといわれております。
また、メインクーンや白い被毛の割合が多い雑種の猫もオッドアイになる可能性があります。猫の中でもジャパニーズボブテイルは、白地の多い三毛猫に現れやすいといわれています。
◆ターキッシュバン
トルコ原産で、トルコ東部のバン湖周辺が発祥地といわれる種類の猫です。猫は一般的に水が苦手ですが水の中で遊ぶのが好きな珍しい猫です。瞳の色はブルー、アンバー、オッドアイなどがあり、大きく丸みのある瞳が特徴的です。
また、体が白く、頭としっぽだけに色がつく珍しいバイカラーが特徴で、この毛柄を「バンパターン」といいます。
◆ターキッシュアンゴラ
こちらもトルコが原産地で、絹のような光沢を放つ並みの美しさから「トルコの生きる国宝」と呼ばれています。ターキッシュアンゴラは、他の猫に比べてやや細身で、引き締まった筋肉を持っているのが特徴的。瞳の色はブルー、アンバー、グリーンゴールド、グリーン、オッドアイなどがあり、気品あふれる猫です。
◆ジャパニーズボブテイル
招き猫のモデルともいわれ、短く丸まったしっぽが特徴的な日本産の猫です。
スラりとしたモデル体型に、常に落ち着いている冷静な性格の持ち主。
瞳の色は基本的に毛色に応じた色ですが、白地の猫にオッドアイが多いです。
◆メインクーン
原産地はアメリカで、メイン州公認の「州猫」として認定されています。
別名「穏やかな巨人」とも呼ばれ、ペットとして飼われている猫の中では最も大きくなる猫の一つです。
また、メインクーンは頭の形が幅広く、丸みを帯びた、くさび形をしています。冬の寒さに対応できるよう分厚く耐水性のある被毛になっています。
瞳の色は毛色に応じた色ですが、ブルー、グリーン、ゴールド、カッパー、オッドアイなどがあります。
オッドアイの猫の性格
オッドアイの猫だからといって他の猫と大きな違いがあるわけではありませんが、オッドアイの猫の多くは、甘えん坊・気が強い・クールで神経質な一面を持っている子が多いです。
白猫の場合は白の被毛がかなり目立つため、天敵に狙われやすいことから警戒心が強く、神経質な一面も多いといわれています。生きていくために、警戒心が強くて神経質の性格にならざるを得なかったともいわれています。
その反面、飼い主さんと関係構築がされている場合は甘えん坊な一面も。
また、独占欲が強い傾向があり、多頭飼いをして同居猫がいる際は喧嘩をしてしまう可能性があるので、多頭飼いには注意が必要です。
オッドアイの猫を飼う時の注意点

一般的な健康の猫よりもオッドアイの猫の場合は、普段の生活から注意が必要なことがいくつかあります。先天的な場合、特に気を付けたい3つのポイントをご紹介します。
◆聴覚障害がある場合
先天的な理由から聴覚障害を持つ猫は、一見不自由がない生活をできているように感じますが、外に出ないよう十分に注意が必要です。
猫を飼う時は当たり前ですが、脱走対策は念入りにすると思いますが、聴覚障害がある場合、音で危険を察知する能力が不十分なので、外へ勝手に出てしまうと事故に繋がる恐れがあります。
また、猫全般的に言えることですが、いきなり後ろから触ったり、驚かせるようなことも危険です。
聴覚障害がある場合、音でまわりの様子を察知できないので、驚くことに対してストレスを感じてしまいます。
◆紫外線に注意
オッドアイのブルーの瞳側はメラニン色素が少ないため、紫外線には特に注意が必要です。
メラニン色素が少ないと、紫外線から目の細胞を守ることができないので、目の病気になるリスクが高いのです。
日中や日差しが強い夏など、強い紫外線はメラニンの少ない虹彩にダメージを与え、白内障や緑内障などの目の病気につながる場合があります。室内で飼っているからと安心せず、直射日光が当たっていないか十分にチェックしましょう。
春~夏にかけては特に紫外線が強いので、季節やその日の時間帯に合わせてカーテンやブラインドで対策するなど、早めの対策が大切です。紫外線対策グッズを使用して十分に対策をしましょう。
◆過ごしやすい環境を整える
先天的な理由から視覚や聴覚に問題が起きやすく、一般的な健康の猫に比べると、外敵や危険から身を守る機能が衰えている可能性があります。
身の周りに危険な障害がないか飼い主がチェックし、生活しやすい環境を整えてあげることが大切です。
神経質な面があるので、ゆったりと過ごせて安心できる環境を用意してあげると安心して生活することができます。
一般的な健康の猫とは違うことを十分に理解して、リラックスできる過ごしやすい環境を作ってあげましょう。
また、聴覚障害の猫の場合、自分の鳴き声に対するフィードバックの調整が上手くできず、静かな環境であるのにも関わらず、大きな声で鳴く可能性があります。
なるべく猫の要求鳴きがないように行動欲求を満たしてあげて、過ごしやすい環境づくりを心掛けましょう。
オッドアイの猫が気を付けたい病気
ブルーの瞳でメラニン色素が少ないことから、紫外線が直接皮膚に届きやすいため、日差しを浴びすぎると日光皮膚炎になる場合があります。
症状として、毛が少ない部分(耳の先端、鼻先、目、口まわりなど)に、赤み・脱毛・かゆみ等の炎症が出やすいです。猫にとって炎症が起きると痒いので、掻きむしって出血してしまうことも…。
これらを放置すると扁平上皮癌に進行し、皮膚細胞の腫瘍が発生して重症化する恐れがあります。その場合は外科切除が必要になるので、早めの予防が大事です。
予防対策としては、紫外線に注意することです。窓ガラスにUVカットのシールを貼ったり、日差しが強い時間帯や紫外線が多い時間を避け、紫外線防止のグッズを使用するなど、できる限り工夫しましょう。
もし炎症などが確認されてしまった場合はすぐに獣医師い相談するようにしましょう。
まとめ
その神秘的な瞳を持つオッドアイの猫は世界で親しまれていますが、先天的な理由から注意しなければならないことがいくつかあるので、健康面や外部環境には十分に気を付けて楽しく安全に生活ができるように心がけましょう。
たくさんの愛情を注ぐほど、飼い主さんに対して甘えん坊になるくらいとっても懐いてくれますよ♪
オッドアイの猫の特徴を十分に理解しながら、楽しく安全に過ごせるようにしましょう。
– おすすめ記事 –
| ・オッドアイの猫はどうして生まれるの? |
| ・「美しい猫」ってどんな猫種?様々な猫種の特徴が知りたい! |
| ・猫の色覚は人間と一緒?どんな色を認識しどんな世界を見ているの? |
| ・【面白ねこ雑学】猫ならでは!?猫の瞳孔が縦に細い理由は? |