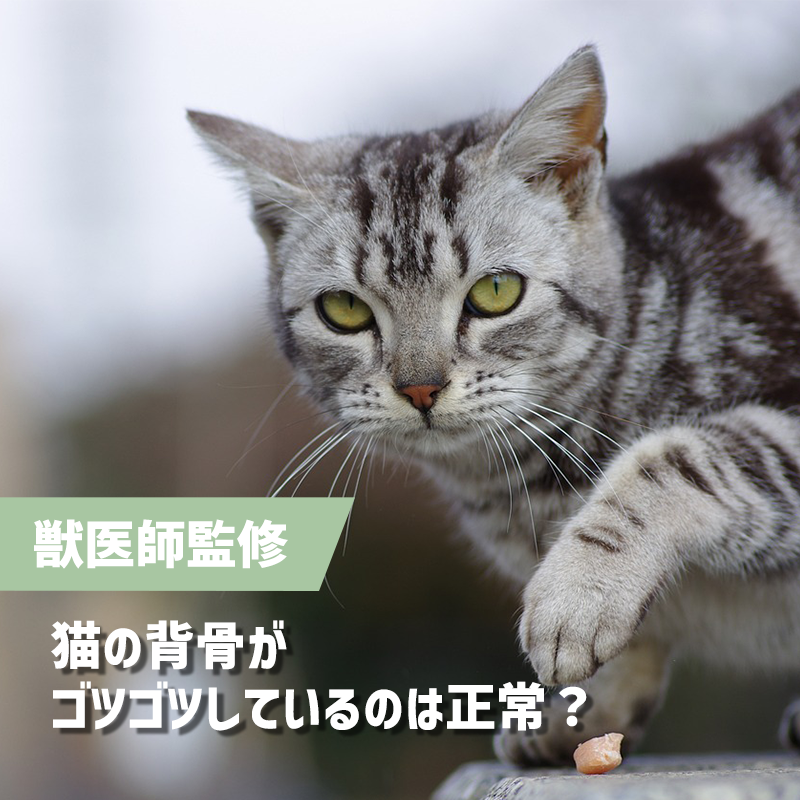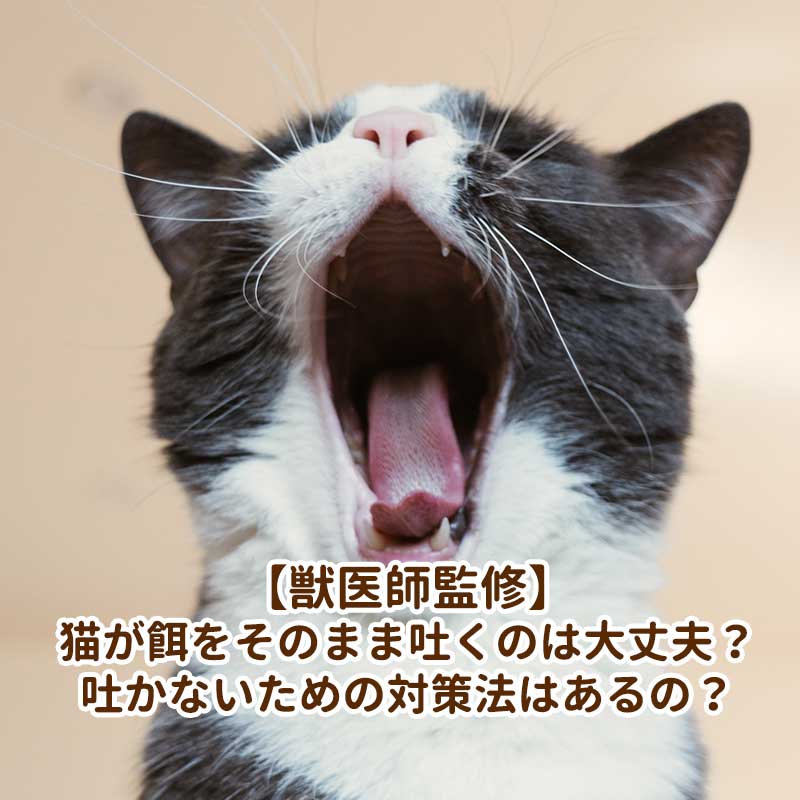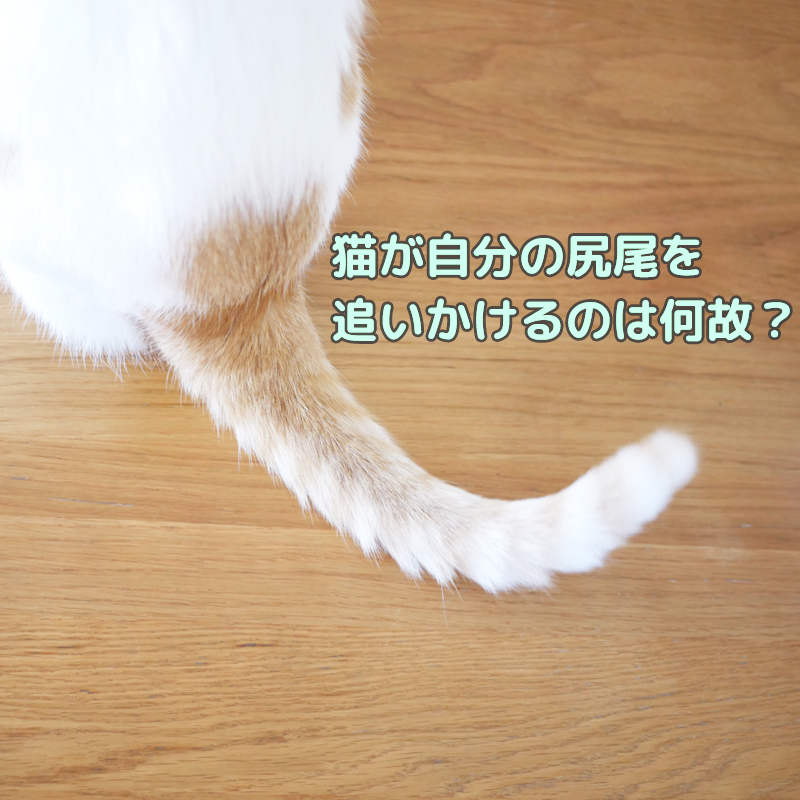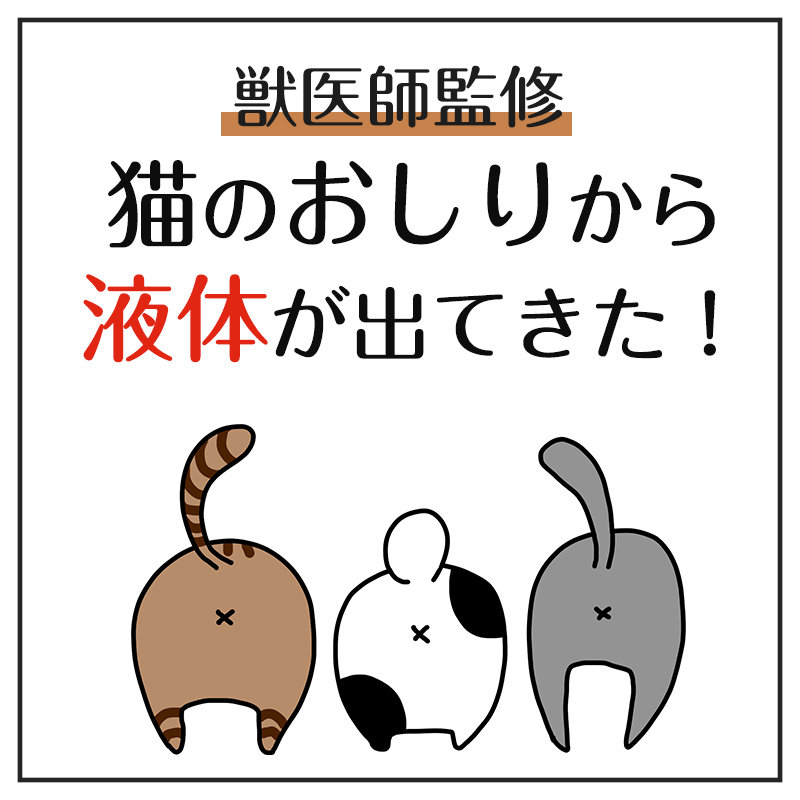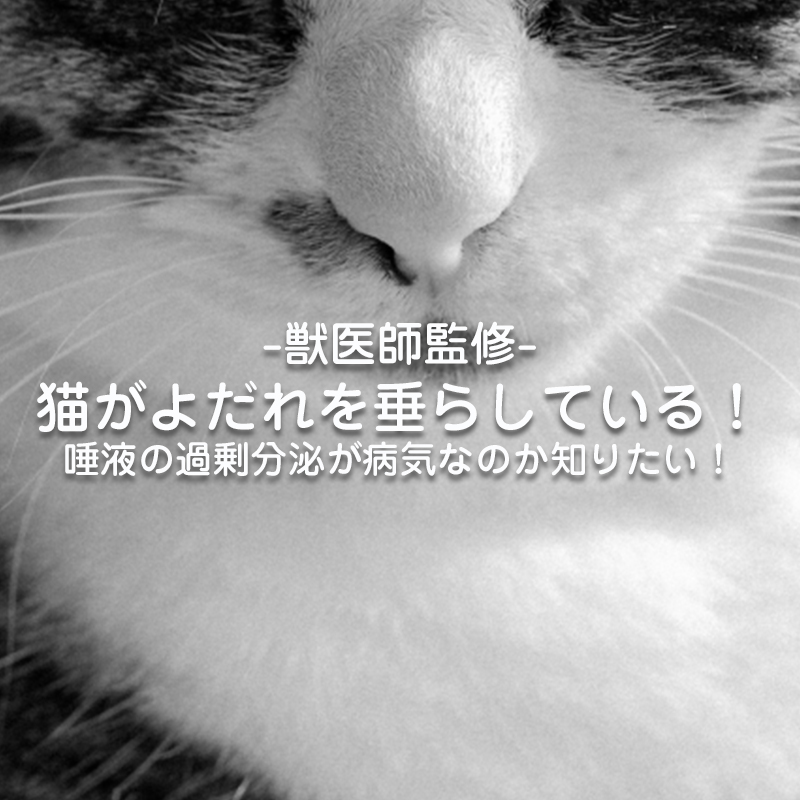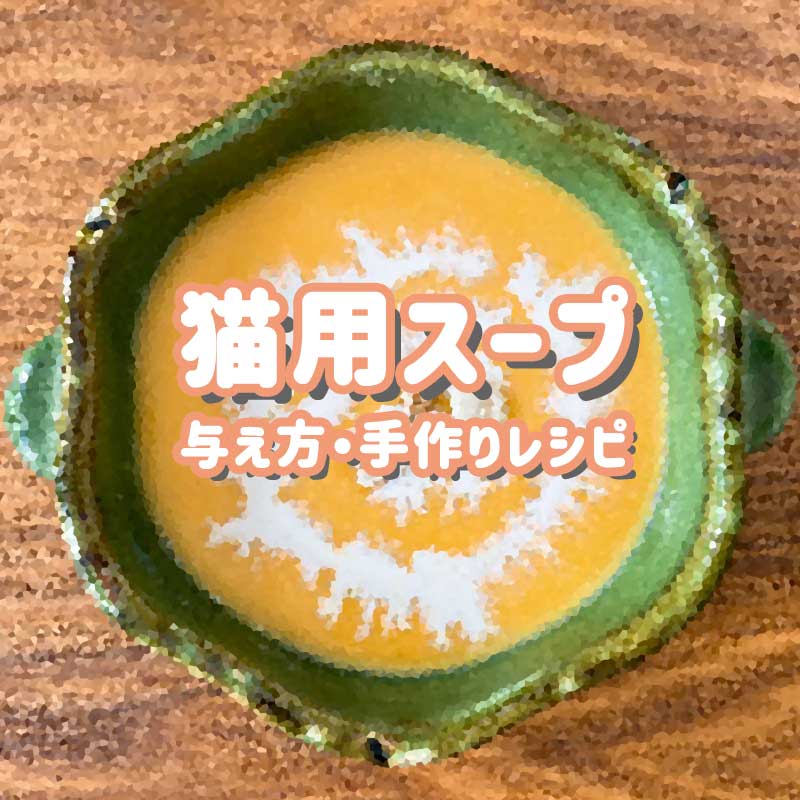「獣医師監修」の記事一覧
-
【獣医師監修】猫の背骨がゴツゴツしているのは痩せすぎ?原因や体型のチェック方法とは
愛猫の背中をなでた時のゴツゴツとした背骨の感触に、「愛猫は痩せているのではないか」と心配し、驚いたことがある飼い主さんもいるかもしれません。この記事では、そんな時に役立つ猫の体型チェックの仕方や、確認する時の注意点、痩せているかもと不安になった時の対処法を解説します。
-
【獣医師監修】猫が餌をそのまま吐くのは大丈夫?吐かないための対策法はあるの?
猫は病気の有無に関係なく、よく吐く動物として知られていますが、ご飯をあげたあとに餌の形状をそのまま吐いてしまうようなことがあれば、愛猫の体調面が心配になってしまいますよね。 餌をそのまま吐いてしまえば、必要な栄養も摂取できませんし、お腹を空かせていたとしても、再度食事を与えても良いのか、悩まれる飼い主さんは多いことかと思います。 なぜ猫は餌の形状がそのままの状態で吐くことがあるのか、どのような原因で嘔吐してしまうのかなど、理由を知った上で適切な対策をできるようにしておきましょう。
-
【獣医師監修】猫が自分の尻尾を追いかけるのは何故?常同行動とその対処法を学ぶ
猫が自分の尻尾を追いかけてくるくると回っている姿は、愛らしい行動に見えます。しかし、あまりにも頻繁に、しつこく尻尾を追いかけるなら、注意が必要です。ストレスや皮膚病、神経障害が原因で、尻尾を追いかけているのかもしれません。このように、同じ行動を頻繁に見せることを「常同行動」と言います。そこで、猫が自分の尻尾を追いかける理由と、その対処法についてまとめました。
-
【獣医師監修】猫は牡蠣を食べられる?栄養素や食べられない魚介類まとめ
牡蠣は欧米では『海のミルク』と言われ、豊富な栄養素を含んでいます。更に、低カロリーという魅力的な食材です。おいしくて栄養豊富な牡蠣ですが、猫が食べても大丈夫なのでしょうか?牡蠣の栄養成分として有名なタウリンは、猫にとっても必須の栄養素の一つです。ここでは、猫に牡蠣を与えてもいい理由や牡蠣の栄養素と、猫が食べてはいけない魚介類についてお話します。
-
【獣医師監修】猫のおしりから液体が出てきた!これは病気?原因と対処法、肛門腺絞りについて解説
愛猫のおしりから液体が出てきたら、驚いてしまいますね。出てきた液体の色や臭いによって原因は異なり、あまり心配しなくてよいものから深刻な病気までさまざまです。考えられる主な原因としては、肛門腺の分泌物や軟便、膀胱炎や子宮蓄膿症などがあります。今回は、猫のおしりから液体が出てくる場合の原因と対処法について解説します。猫の肛門腺絞りについても参考にしてみてくださいね。
-
【獣医師監修】猫は油を舐めても大丈夫?油の効果と危険性について
猫が油を舐めてしまった!という経験はありませんか? 油の種類によっては、少し舐めた程度では問題がないことが多いですが、中には猫にとって有害な油もありますので、十分に注意しなければなりません。 大切な猫の健康と安全を守るために、油の安全性とリスクについてよく理解しておきましょう。
-
【獣医師監修】猫が咳をする原因とは?考えられる病気や予防方法について
猫も人と同じように咳をすることがありますが、人のように日常的に咳をすることはありません。同じ咳でも心配のいらない咳、病気が隠されている咳など、理由はさまざまです。 猫の咳には、どのような原因があるのでしょうか。また、咳をする場合に考えられる病気や予防法についてご紹介します。
-
【獣医師監修】猫の鼻水や涙は要注意!考えられる病気と症状
猫も鼻水や涙を流すことがあります。猫の鼻から鼻水が出るのは生理現象で、猫の鼻が湿っていることは普通です。しかし、猫の鼻水や涙がずっと止まらないのは病気のサインの時です。様々な病気がありますが、猫風邪、副鼻腔炎、流涙症、白内障といった病気が考えられます。それぞれの症状や原因、治療法、予防法についてお伝えします。
-
【獣医師監修】猫がよだれを垂らしている!唾液の過剰分泌が病気なのか知りたい!
猫はとてもキレイ好きな動物なので、食事のあとはもちろん、時間さえあれば必死にグルーミングをして、体を清潔に保っていますよね。 しかしそんなキレイ好きの猫が、よだれを垂らしていた場合はどうでしょうか? 何かよっぽどの理由があるのでは、と疑わずにはいられませんよね。 猫がよだれを垂らしている場合は、体に何かしらのトラブルが起きていると考えられますが、一体どんな原因が隠されているのでしょうか?
-
【獣医師監修】猫の水分補給にはスープがおすすめ!手作りレシピと与え方
猫はあまり水を積極的に飲まない動物です。猫の祖先は砂漠で暮らしていたため、猫も少ない水分で体を保持できると言われています。一方、猫に一番多い病気は腎臓病や尿路結石であることもよく知られています。これらの病気は、日ごろの水分摂取が足りないと起こりやすくなります。そこで有効なのが猫のためのスープです。 今回は猫用スープについて、メリットや手作りレシピをご紹介します。
記事に関するお問い合わせはこちら