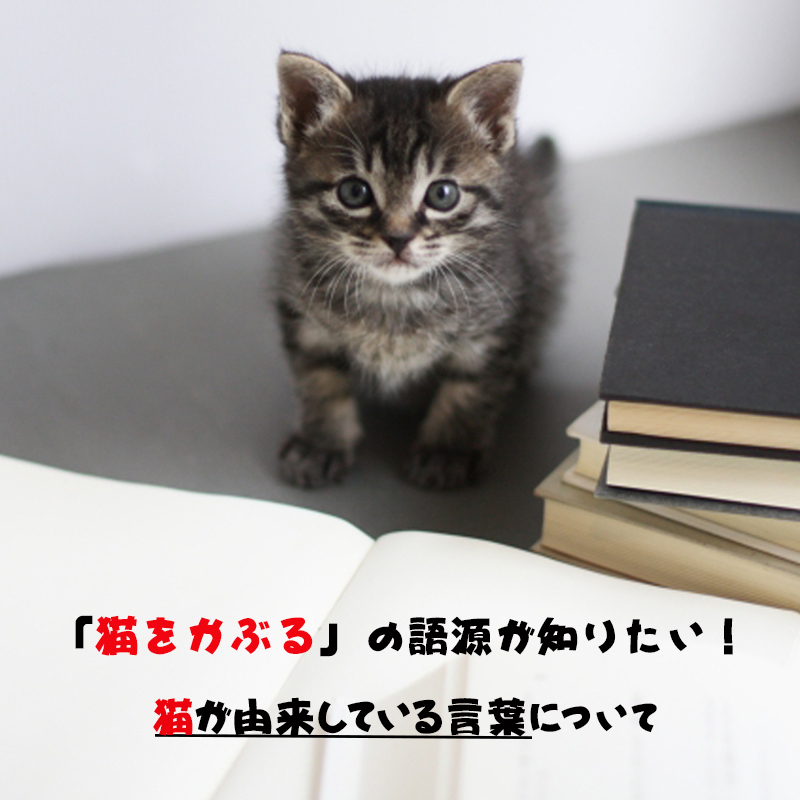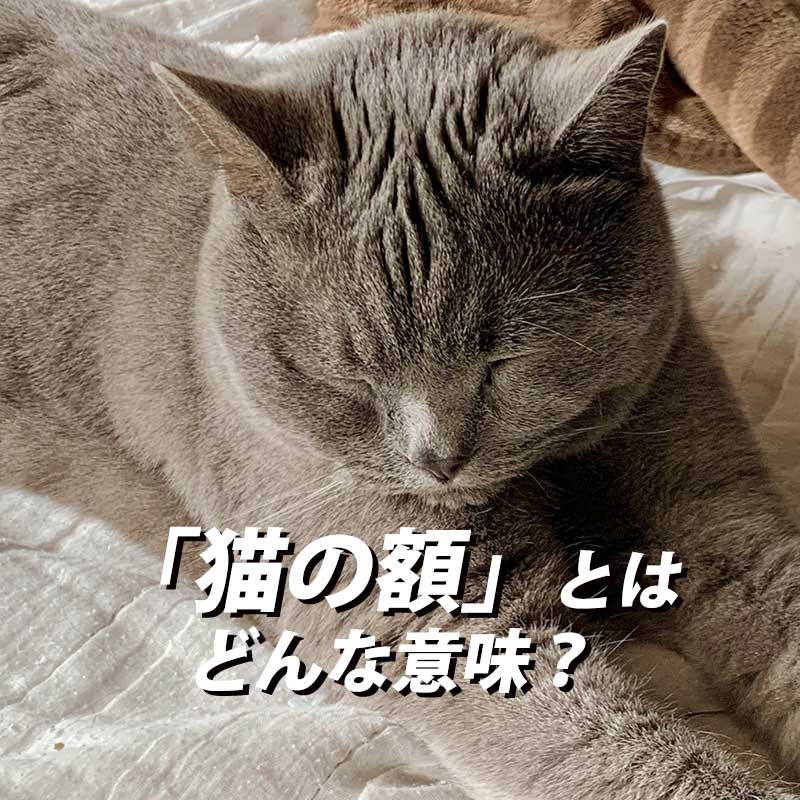1.猫をかぶる
2.猫だまし
3.ネコババ
4.窮鼠猫を噛む
5.猫舌
6.借りてきた猫
7.猫の手も借りたい
8.猫に小判
9.猫背
10.猫撫声
11.猫の額
12.猫の前の鼠
13.猫に鰹節
14.まとめ
1.猫をかぶる
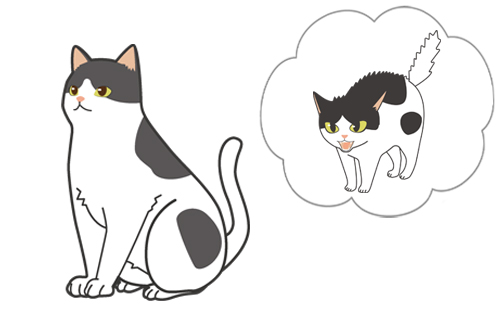
人前で、本当の性格を隠して「大人しい」「おしとやか」を演出する意味の言葉です。
猫と言えば、いつもはゴロゴロと寝て過ごすことが多く、おっとりしたマイペースな印象がありますよね。
時には飼い主さんに甘える様子も見せて、とにかく可愛らしい動物です。
そうかと思えば、急に威嚇行動をして噛みつきや引っ掻きが見られることも…。
本当は荒々しいところもあるのに、普段はその様子は見えません。
そんな猫の行動が由来となった言葉が「猫をかぶる」のようです。
特に、女性が普段の性格を隠して、大人しく清楚な雰囲気をアピールしているときに、この言葉を使うケースが多いでしょう。
とても活発な人が、わざと大人しく演出している様子です。
2.猫だまし
猫だましという言葉ですが、聞いたことがあっても「どんなときに使うんだっけ?」という方もいるのではないでしょうか。
猫だましは、相撲においての戦法のひとつなので、相撲をよく知る人ならお馴染みの言葉かもしれませんね。
しかし、逆に相撲がよく分からないという人は「猫だまし」と聞いても、その意味がピンとこないでしょう。
猫だましは、戦いの途中で相手の意表をついて目の前で手をたたき、相手が一瞬目を閉じたタイミングで勝ちを取りに行く…という戦い方です。
普通では勝てないような相手でも、ちょっとした隙をついて仕掛けていくことの例えと言えるでしょう。
猫が語源となっているのは、「猫が敵だと思って猫じゃらしを前足で掴もうとする様子」が「力士が行う戦法」と似ているからのようです。
猫は相手のちょっとした動きにも反応できる俊敏さの持ち主。
小さな力士ならではの素早い動きが、猫の動きと似ているからかもしれませんね。
3.ネコババ
ネコババは、世間的にも浸透している言葉ですよね。
聞いたことがある、または使ったことがあるという方も多いでしょう。
一般的に、「拾ったものをそのまま自分のものにする行動」と捉えている人が大多数かと思います。
実は、ネコババは“猫糞”と漢字で表され、猫の糞が関係しています。
江戸の頃、子供達が糞のことを“ババ”と呼んでいたそうです。
猫には、糞をした後、見えなくなるように砂に隠すという習性があります。
その流れで、元々は「悪いことをした後に隠すこと」という意味だったのですが、現在では「拾ったものを自分のものにする」という意味で使われることがほとんどです。
4.窮鼠猫を噛む
これは、ネズミが猫を噛む様子が例えられた言葉です。
本来であれば、ネズミは猫に追われる立場。
大きな猫には勝てないことが分かっていますから、いつも逃げ回っているイメージですよね。
しかし、本当に切羽詰まっている状況、窮地に追い込まれたらネズミだってただ追われているわけにもいきません。
勝てるかどうかは分からなくても、立ち向かうことができます。
「窮鼠猫を噛む」という言葉は、普段は弱い鼠だって、最大限の力を発揮すれば強敵である猫にも向かっていけるという例えです。
弱い人を追い詰めても、いつか反撃されるかもしれないという意味が込められている言葉と言えるでしょう。
5.猫舌

熱々の食べ物や飲み物が苦手なとき、「猫舌だから」という表現をするのは、みなさんよくご存じかと思います。
実際に熱い飲食物が苦手な人は、普段から使っている言葉かもしれません。
でも、なぜ“猫”なのだろうと疑問に感じたことがある方も多いでしょう。
実は、猫舌という言葉の誕生は古くさかのぼり、なんと江戸時代なのだそう…。
江戸時代には、すでに猫は人間と共に暮らしていました。
ペットとして可愛がられることもありましたが、「ネズミ退治」のために飼われていたと言われています。
当時は、キャットフードなるものはありませんでしたから、猫にも人間同様に調理後の温度の高い食事を与えることがありました。
しかし、猫は人間と違って「アツアツの食事」は食べませんでした。
それが広く知れ渡った結果、“猫舌”という言葉が一般的になじんでいったのです。
6.借りてきた猫
「借りてきた猫」という言葉は、いつもと違って静かになるという意味で使われることが多いです。
特に、普段結構賑やかなのに、違う場所に行った時に緊張などから静かになる人によく使われます。
昔は、ネズミ対策で猫を飼っている家も多かったものです。
猫は機敏で狩猟がうまい動物ですから、もちろんネズミも捕獲してくれます。
猫はすべての家で飼っていたわけではないため、猫を飼っていない家の人が、よその家から借りてネズミを捕獲してもらおうというケースもあったようです。
愛猫家の皆さんなら知っているかと思いますが、環境の変化にナーバスな猫は、人の家に行っても緊張から本来の能力を発揮できません。
せっかくネズミを退治してもらうと借りてきても、まったく何もしてくれなかった…、そんな背景から「借りてきた猫」という言葉が誕生したようです。
また、「猫をかぶる」と似たように思えるかもしれませんが、ニュアンスが異なります。
「猫をかぶる」は、自分を偽って演出するイメージです。
「おとなしい・おしとやか」と見せたくて、わざと演技をするのが“猫をかぶる”と言えるでしょう。
しかし、「借りてきた猫」の場合、本人は無意識に静かになっているケースが多いです。
同じく、“猫”と“借りる”が含まれている言葉ですが、ちょっと使い方が異なるのですね。
7.猫の手も借りたい

「猫の手も借りたい」も、普段よく耳にする猫を使った言葉です。
人手が足りなく、とにかく忙しいとき、「手伝ってくれるなら誰でもいい」と思うことがありますよね。
そこで、「猫の手も借りたい」という表現を使うケースがあります。
でも、現実的に考えると、それほど忙しいとき、猫が力になってくれるとは思えませんよね。
それなのに、どうして“猫の手”なのでしょうか。
実は、この言葉、実際に「手伝ってほしい」というよりも、「猫が手伝ってくれるとは思っていないが、そんな猫の手さえも欲しくなるほど忙しいのだ」という例えなのです。
この言葉ができたのは江戸の頃ではないかとも考えられています。
当時の猫も、現在と同じく、普段はのんびり寝て過ごすスタイルが一般的でした。
忙しいときに、近くでゴロゴロゆっくりしている猫を見て「寝ているなら手伝ってほしいくらいだ」と溜息まじりに思ったのが由来では…と考えられています。
8.猫に小判

「猫に小判」という言葉は、価値の分からない人に価値あるものをやっても、結局は役に立たずにもったいないことを例えたものです。
“小判”が使われていることから分かるように、ずいぶん古くに誕生した言葉です。
当時から猫は人間の身近にいた動物ですが、とてもマイペースな動物でした。
もちろん、小判を見せたところで「お金だ~!」と興味を示すことがありません。
元々、猫は自分が興味なければ無関心なところがあります。
自分のペースで周囲に接する動物です。
そんな背景から、猫を使った言葉となったようです。
また、「豚に真珠」「馬の耳に念仏」など、ほかの動物を使った同じような意味合いの言葉もあります。
9.猫背
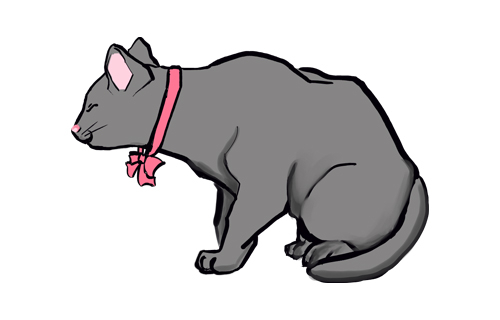
人間の背中が丸い様子、前かがみになって姿勢が悪い様子を「猫背」という言葉を使って表現することがあります。
猫背は体に負担がかかり、肩こりや頭痛、腰痛の要因にもなる症状です。
しかし、どうして“猫”なのか不思議ですよね。
確かに、猫が座っているときの様子を見ると、背中が丸みを帯びて前かがみになっている感じがします。
猫は運動神経が良い動物として知られています。
瞬発力やスピードなどを備えるために、猫の体の骨の数は人間と比べて多いのです。
それが、しなやかな動きにつながっています。
骨の数が多いからこそ、曲がる部分が多く、丸みを帯びてしまうのでしょう。
また、猫は狩猟をするとき、身軽にジャンプをします。
はじめに丸く背骨を縮めておくことで、チャンス到来のタイミングで一気に動くことができます。
人間で言う“猫背”とは、姿勢の悪さを表現する言葉です。
一方、本家の猫にとっての“猫背”は、しなやかな動きを作り出すための原動力となる機能的なものと言えるでしょう。
10.猫撫声
猫撫声とは、媚を含んだような甘い声色をたとえた言葉です。
「誰かに頼み事をする」「ご機嫌とりをする」などの時、相手に対して甘えの感情も入っていますから、いつもと違った甘ったるい声を出す方も多いかもしれません。
これは、猫が人間に撫でられたときに出す声が柔らかいところが由来となった言葉のようです。
11.猫の額
猫の額とは、「狭い場所」を表現するときに使うことがあります。
とても狭い庭を「猫の額ほど…」と謙遜する使い方もあるものの、実際、本当に狭いところを指すケースもあります。
人間の額は、眉毛の上から髪の生え際までという感じがしますが、猫の額はどのあたりなのでしょうか?
そもそも、猫は顔自体が小さく、「額なんてあるのだろうか」という気もしますよね。
つまり、「どこにあるか分からないほど小さな額」の持ち主である猫を使って、狭い面積の場所を“猫の額”というようになったのです。
この言葉、誰かに家や庭の広さを褒められたときに、「いやいや、猫の額ほどなんですよ」と謙遜する使い方が一般的。
そのため、自分以外の相手の家などに対して使うのはNGなので気をつけなければいけませんね。
12.猫の前の鼠
「猫の前の鼠」とは、足がすくんで動けない様子や、とにかく怖い様子を表現した言葉です。
猫にとってのネズミは、狩猟のターゲット的存在。
見つけたら本能的に追いかけますが、ネズミは捕まるまいと必死で逃げます。
それでも、追い詰められて目の前に猫が立ちはだかると、怯えて動けない状況となるでしょう。
13.猫に鰹節

「油断ができない」「過ちが起きやすい状況」「とても危険な様子」を例えたのが猫に鰹節という言葉です。
猫は鰹節が大好物ですから、近くに置けばいつ食べられてしまうか分かりませんよね。
元々、この言葉は「猫に鰹節の番をさせる」でした。
猫に鰹節の番をさせても、大好物を目の前にして猫は我慢できませんよね。
すぐに食べられてしまう危険な状況です。
そんな猫の行動から作られた言葉のようです。
まとめ
いかがでしたか。
ふだん使っている言葉も多くあったのではないでしょうか。
なかには、いつも使っているのに、語源がよくわからず使っていた…という方もいるかもしれません。
何気なく使っている言葉も、意味や由来を知ると面白いものです。
猫の行動や体が語源となっている言葉の意味を知ると、次は使い方も変わってくるかもしれません。
良い意味の言葉、悪い意味の言葉、日常的に結構使う言葉など、私たちの言葉には猫がたくさんいます。
言葉ができる段階で、身近だった猫が語源となった言葉は多いです。
古ければ、江戸時代などから使われていた言葉もあり、猫が長らく人間の身近な動物だったことがうかがえますよね。
今回、お伝えした言葉以外にも“猫”が使われた言葉はたくさんあります。
次に猫が関連する言葉を使うときには、ぜひ語源を意識しながら使ってみてくださいね。
– おすすめ記事 –
| ・猫はcatだけじゃない!猫に関する英語表現、鳴き声、ことわざについて |
| ・猫を見ると天気予報が分かる?顔を洗うと雨が降るって本当なの? |
| ・「猫は三年の恩を三日で忘れる」は本当?猫に忘れられることを防ぐには? |
| ・猫の好きな色が知りたい!猫は色を判別できるの? |