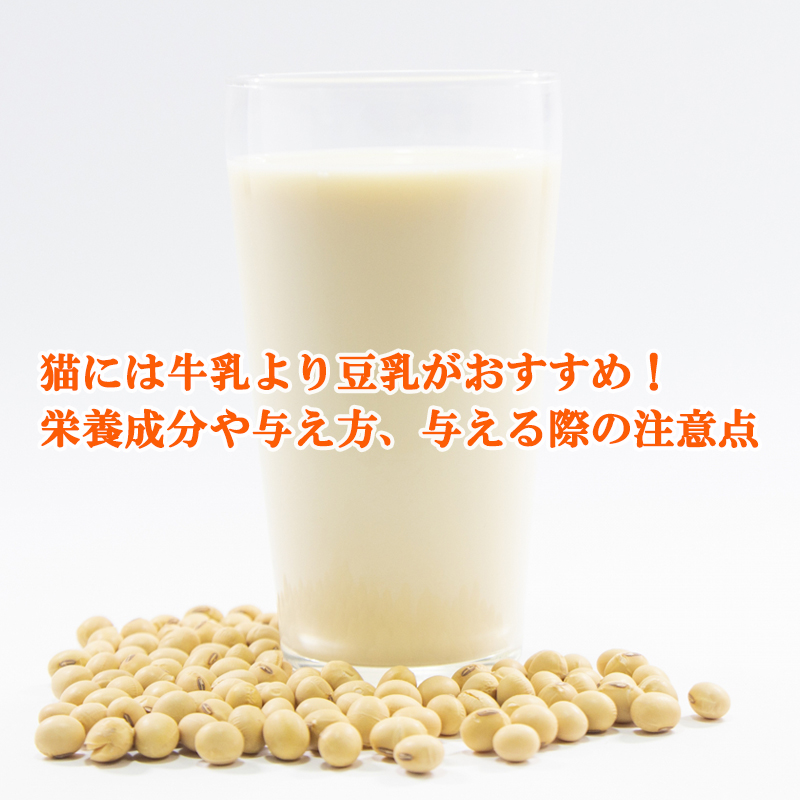1.あんこは何でできている?
1-1.あんこの原料
1-2.あんこの栄養素や効果
2.猫にあんこを与えるのはNG!
2-1.砂糖は肥満や糖尿病につながる可能性
2-2.砂糖なしのあんこは大丈夫?
3.猫があんこをほしがる時には
3-1.砂糖なしのあんこを与える
3-2.あずきを茹でる
3-3.別のおやつで気をそらす
4.まとめ
あんこは何でできている?

「あんこ」とは漢字で「餡子」と書き、原材料となる豆を煮詰めて練った、ペースト状のものを指します。
日本発祥の甘味となる和菓子の主要素となることからも、常に身近な食べ物として昔から親しまれていますよね。
あんこと聞くと、強い甘みのある餡を思い浮かべますが、明確な定義などは存在しているのでしょうか?
◆あんこの原料
あんこは「小豆(あずき)」を柔らかく煮詰め、そこに砂糖を加えたものをあんこと呼ぶのが一般的です。
しかし、原材料が豆であり、そこに砂糖を入れて甘みをつけることは十分条件であって、必須条件ではないとも言われています。
今回の記事でご紹介していくのは、豆を煮詰めて甘みをプラスしたあんこにスポットを当てていますが、あんこはなかなか奥の深い食べ物であることがうかがえますよね。
小豆の粒を崩さず残したものは「粒あん」、小豆の薄皮を取り除いてペースト状にしたものが「こしあん」と、和菓子には欠かすことのできない主役級の食べ物と言えるでしょう。
◆あんこの栄養素や効果
あんこの原材料となる小豆には、さまざまな栄養素が含まれています。
食物繊維やポリフェノールが豊富な上に、ビタミン類やミネラル類も含まれているので、さまざまな効果が期待できる嬉しい食材と言えますよね。
また、小豆の薄皮には「サポニン」と呼ばれる栄養素が含まれており、強い利尿作用や抗酸化作用があるので、血液中のコレステロールや中性脂肪の生成を抑え、脂質の代謝を促すといった効果が望めます。
食物繊維が多く含まれているということは、便秘の解消にも繋がりますし、小豆の赤い色素となる「アントシアニン(ポリフェノールの一種)」には、脂肪の吸収を防いで血液中の中性脂肪の値を低下させてくれる働きをしますので、肥満予防にも繋がると考えられます。
さらに小豆に砂糖を加えることによって、「メラノイジン」といった物質が生成され、抗酸化作用が高まることにより老化防止へと導いてくれるのです。
こんなにも豊富な栄養素が含まれるあんこですから、猫に与えても問題がないようにも思えますが、実際のところはどうなのでしょうか?
猫にあんこを与えるのはNG!
猫の味覚は「甘味」を感じられないとは言われていますが、猫ちゃんの中には甘いものを欲しがる子も多いですよね。
そのような猫ちゃんが存在していることを聞くと、人間と生活を共にしてきたことにより、食べ物の嗜好や体の構造が進化していったのではないか、と考えることもできるのではないでしょうか。
また、猫は嗅覚が優れているので、小豆のニオイを好んだり、飼い主さんが食べているものに対して興味を持ったりするので、このような理由からもあんこを欲しがるのかもしれません。
栄養価の高いあんこであれば、もし猫が欲しがったとしても、与えても良い気がしますが、あんこにはたくさんの「砂糖」を使用しているので、正直なところ猫に与えるべきではない食べ物と言えます。
猫があんこをたべることによって、以下のようなリスクが生じますので、猫があんこを欲しがるからといって、欲しがった分だけ与えるようなことは絶対に止めておきましょう。
◆砂糖は肥満や糖尿病につながる可能性
あんこは砂糖を加えてペースト状にした食べ物ですので、甘さのある調味料を必要としない猫にとっては、体に害を来す可能性があると考えられますよね。
小豆に砂糖を加えることによって、抗酸化作用が高まる物質ができ、老化防止に役立つ効果は期待できますが、そのほかの部分で体に害を来すのであれば、摂取しないに越したことはありません。
小豆は砂糖を加えてあんこにすることで、糖質量が一気にアップします。
食べた量が少なかったとしても、人間と猫とでは体の大きさも違いますし、糖分を多く摂取すれば肥満や糖尿病のリスクも高くなってしまうことでしょう。
愛猫があんこを欲しがったとしても、健康のことを考えて与えないようにしてください。
◆砂糖なしのあんこは大丈夫?
あんこを欲しがる猫ちゃんの中には、何としてでも食べようとする子も居ますので、与えられないと分かっていながらも、与えられないことにもどかしさを感じる飼い主さんも多いことでしょう。
砂糖が加えられているあんこを猫に与えることは絶対にNGではありますが、砂糖を加えていないあんこであれば、少量を与えることは問題ありません。
小豆に含まれる栄養素は猫にとって嬉しい成分も多いので、添加物を加えていないあんこであれば、猫に与えることができるのは喜ばしいことですよね。
しかし、小豆の薄皮は消化に悪いので、皮が残ったままの粒あんを大量に与えてしまえば、下痢や嘔吐などの症状が出ることもあるので注意が必要です。
粒あんを与える場合には細かく切ったものを少量与えるようにし、加糖されていないこしあんを準備できるのであれば、こしあんを少量与えるようにしましょう。
猫があんこをほしがる時には

基本的に猫にはあんこを与えるべきではありませんが、どうしても欲しがる場合には、どのようにして対処するべきかを考えておかなくてはいけませんよね。
欲しがった分加糖のあんこを与えることはもちろんNGですが、どのような対処法を用いるべきなのでしょうか。
◆砂糖なしのあんこを与える
猫があんこを欲しがった場合、砂糖を加えていないあんこであれば、前述した通り少量与えるのであれば問題ありません。
しかし、加糖していないあんこが安全だからといって、様子を見ずに大量に与えることや、毎日摂取させるようなことはしないでください。
猫ちゃんの中には小豆のアレルギーを持っている子が居るかもしれませんし、小豆を食べることによって上手に消化できずに、下痢や嘔吐をしてしまう子が居る可能性も否めませんよね。
愛猫の安全を守るためにも、欲しがった分だけあんこを与えるようなことはせず、様子を見ながらあんこを少量与えるように心掛けるようにしましょう。
◆あずきを茹でる
あんこのニオイに興味を示す子であれば、小豆を茹でてその後何の味付けもしていない状態のものを食べさせてあげてみてはいかがでしょうか。
ニオイに興味を示すものの、食べてみて美味しいと感じなければ、今後あんこのニオイを嗅いでも興味を示す可能性も低くなることも。
加糖されたあずきを欲しがるぐらいであれば、ただ茹でただけの小豆を食べた方が体への負担も少ないので、あんこのニオイに釣られて欲しがる子であれば、一度はこの方法を試してみてはいかがでしょうか。
◆別のおやつで気をそらす
猫は嗜好が個体によってそれぞれ異なりますので、その子の好みを知っておくことも大切ですよね。
興味を示したり好んで欲しがったりするものを、飼い主さんが阻止することはとても気が引ける行為ですので、人間の食べ物を欲しがった際に、それ以上に愛猫が好むようなおやつを準備しておくのもおすすめです。
もちろんその際に選ぶおやつは加糖されていない、猫用のおやつを選ぶことが一番ではありますが、人間が食べているものに興味を示して欲しがるようであれば、猫にも安全な食材を少量与えるのであれば問題ありません。
その際にはしっかりと自分自身で情報を収集し、猫に安全な食材を知る必要はありますが、猫と一緒に暮らしているのであれば必要な情報となるので、この機会に猫が口にしても安全な食材を調べてみてはいかがでしょうか。
まとめ
日本を代表するお菓子に多く使用されているあんこに、興味を示す猫ちゃんは、不思議なことにとても多いですよね。
日本に住むからなのか、日本人の気持ちに寄り添っているのか、理由は分かりませんが、その気持ちに応えてあげたいと思ってしまうのが、飼い主さんの本音と言えるのではないでしょうか。
しかし、あんこにはたくさんの砂糖が加えられていることもあり、あんこをそのまま猫に与えてしまうのは望ましくありません。
原材料となる小豆の栄養素が高かったとしても、加糖されていることによって、猫の体に多大な害を与えることも否めませんので、欲しがったとしても与えないことが適切と言えるのではないでしょうか。
猫の味覚は生後1年以内に決まってしまうので、その間に様々な食べ物を食べさせてしまえば、成猫になっても人間の食べ物に興味を示すようになってしまうので、極力猫の嗜好を助長しないような心掛けも必要となりますよね。
基本的に人間の食べ物は猫に与えるべきではないので、人間の食べ物を欲しがった際にも対処できるように、猫が喜ぶ猫用のおやつを事前に準備しておき、常に対処できるようにしておくようにしましょう。
– おすすめ記事 –
| ・猫はナッツを食べても大丈夫?もっとも危険度の高い4種類とは? |
| ・牛乳よりヤギミルクが猫におすすめである理由は?栄養素と与え方も |
| ・【獣医師監修】猫にチョコレートはダメ!致死量や舐めた時の対処は? |
| ・猫がプリンをほしがってくる!与えても問題がないのか知りたい! |