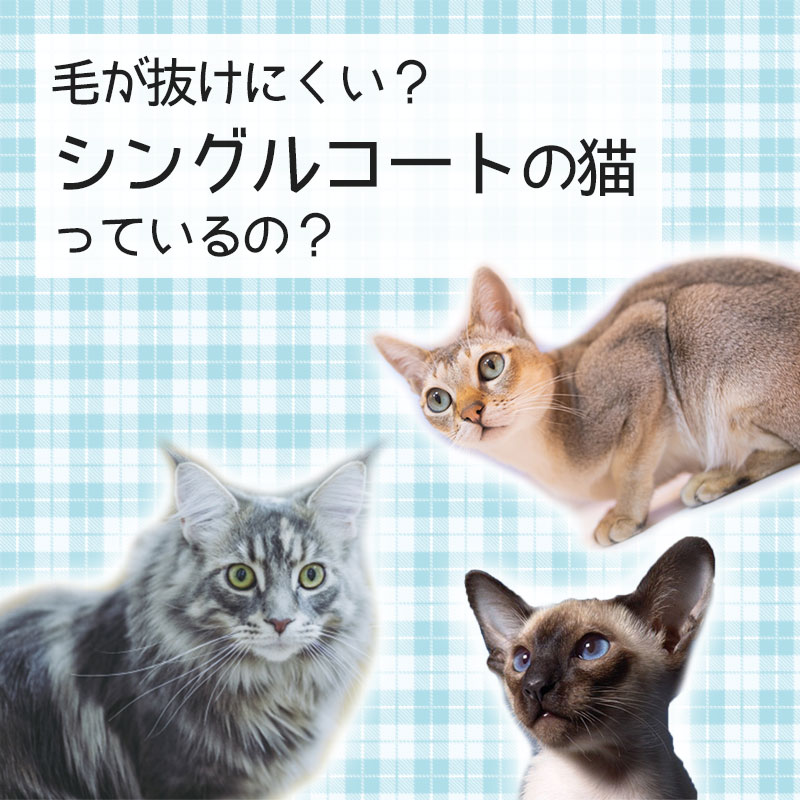猫の鼻の健康状態とは?

猫にとって鼻はとても大切な器官となりますが、一般的には常に湿っている状態であることが知られていますよね。
当たり前のように「猫の鼻は湿っている」と思っている方は多いと思いますが、なぜ湿っている必要があるのか、よく知らないといった方も少なくないはずです。
猫の鼻は湿っていたり乾いていたりするように、鼻の状態によって健康かどうかを示すサインとしての確認が可能です。
まずは基本的になぜ猫の鼻が湿っているのか、その理由を見ていきましょう。
猫の鼻に触れてみるとひんやりとした液体で湿っていますが、この水分が何なのか、なぜ湿っているのかをご存じでない方も多いのではないでしょうか。
猫にとって嗅覚は聴覚の次に優れた感覚となり、人間と比べると数万倍の嗅ぎ分ける能力を備えています。
嗅上皮(きゅうじょうひ)といった粘膜でニオイを感知する神経細胞(嗅細胞・きゅうさいぼう)が、人間は500万個あるのに対して猫は2億個あるとも言われているように、猫にとって嗅覚は生きていく上で重要な感覚であることが分かりますよね。
このように優れている感覚だからこそ、さまざまな情報を持つニオイの粒子が嗅細胞に吸着しやすくするため、猫の鼻は鼻腔内にある腺(腺細胞)から出る分泌物により、常に湿った状態になっています。
この分泌物は神経により調節されているため、交感神経が優位になったときは鼻が湿るようになり、副交感神経が優位になっているときには鼻が乾きやすくなるようです。
そのため、運動しているときや興奮しているときには分泌物が増えますが、さまざまな情報をニオイからキャッチしていることがうかがえます。
猫の鼻が乾いている理由

猫の鼻が湿っているメカニズムは分かりましたが、なぜ乾いているときがあるのかも気になるところですよね。
猫の鼻が乾いている場合には、どのような理由が挙げられるのでしょうか。
基本的に猫の鼻が乾いているときが一時的な乾燥であれば、とくに問題視をする必要はありません。
もともと猫自身の生活サイクルの中で、睡眠中、寝起き、リラックスしているときには分泌物が減少すると言われており、猫の鼻は自然と乾くようになるようです。
このように、わざわざ情報を必要としないタイミングでは猫の鼻は乾きやすいため、鼻が乾いていることは必ずしも病気などに繋がらないことを覚えておきましょう。
一時的な乾燥や空気の乾燥以外で猫の鼻が乾いているときは、健康状態に問題が発生している可能性も否めません。
元気がなくじっとしている様子が見られて鼻が乾いている場合には、発熱や脱水などの全身状態に関わる病気を発症しているケースもあります。
そのほかにも、鼻腺が詰まっていたり老化が関係していたりする場合もあるため、鼻の乾燥以外にも症状が出ていないかの確認を怠らないようにしましょう。
猫がストレスや不安を感じたときにも、鼻が乾燥することがあります。
アクティブに活動しているときは湿っている猫の鼻ですが、ニオイを嗅いで情報を得る必要のないリラックス状態のときは乾くことがあるため、前向きな気持ちになれないようなときにも鼻は乾きやすくなるようです。
このようなときには前述してある通り副交感神経が優位になっているため、腺細胞が抑えられることにより、鼻が乾燥しやすくなると考えられます。
猫の鼻が乾いている時の対処法

基本的に猫の鼻は湿っているため、乾燥していると気づいたときには心配になってしまう飼い主さんは多いと思いますが、一時的な乾燥でしたらそのまま様子をみても問題ありません。
長期的に鼻が乾いている様子が見られる、病気の不安が拭えない場合には、飼い主さん側でできる対処法はあるのでしょうか。
室内が乾燥していて換気が悪い状態が続いてしまうと、風邪などに感染しやすくなってしまうため、加湿器などを利用してある程度の湿度を保つことも大切です。
猫にとって快適な湿度は50~60%程度と言われているため、室内の湿度がこれよりも低い場合には意識的に適切な湿度に調整してあげてください。
また、陽の当たる場所を好む傾向がある猫ちゃんの場合は、陽に当たって鼻が乾いてしまうこともあるため、日よけ対策をしつつ別の場所に寝床をつくってあげるのも良いでしょう。
脱水が疑われる場合には、愛猫が摂取する水分量を増やす工夫をしてみましょう。
猫はあまり水を飲まない動物としても知られているため、飲水スポットの見直しをしつつ、自ら飲んでくれるような対策が重要となってきます。
ドライフードを与えているようでしたらお湯でふやかすなどをして水分量を増やす、ウェットフードを取り入れるなども効果的です。
飲み水は常に新鮮なものを用意するようにし、飲水場を増やす、器の素材を変える、流水タイプの給水器を使用するなどもおすすめとなります。
猫の鼻は常に湿っているわけではなく乾燥することもあるため、基本的には様子をみるだけで問題ありませんが、乾いた状態が長引いている場合には病気を疑ってしまいますよね。
どのようなタイミングで動物病院を受診し、獣医師さんに相談すべきか、という点も悩みどころですが、鼻が乾いている以外にも何かしらの症状が出ている場合には、様子をみるようなことはせずなるべく早めに動物病院を受診するようにしてください。
病気で鼻が乾いている場合には、熱がある、食欲が低下している、元気がない、眠る時間が多くなっている、排泄の状態がいつもと違うなどの症状が出ることがあるそうです。
猫の健康管理のポイント

猫は人間の言葉を喋れないため、一緒に暮らしている中でいかに飼い主さんが愛猫の健康維持に気付いてあげられるかがポイントになってきます。
愛猫の健康管理をしていく上で以下のことに注意するようにし、長生きできるようにサポートしていきましょう。
猫は人間よりも速いスピードで歳をとっていくため、定期的な健康チェックは欠かせませんよね。
飼い主さんが愛猫の健康に無頓着で居続けてしまうと、何かしらの病気を患っていたとしても気付くのが遅れてしまい、動物病院に連れていったときにはかなり重症化しているケースも少なくありません。
愛猫の健康を守ってあげられるのは飼い主さんだけとなるため、日頃から異変はないかの確認をするようにしつつ、最低でも年に1回は動物病院を受診して健康診断を受けるようにし、愛猫の身体が健康かどうかの確認も怠らないようにしてください。
異変に気付くためのポイントとしては、毎日のスキンシップでは愛猫の様子をよく観察する、ボディタッチをして異常がないかの確認なども大切ですし、食欲が低下していないか、元気はあるか、排泄は問題なくできているかなどの確認も大切です。
鼻の湿り具合は目視でも確認可能ですが、乾燥が気になったときには鼻がすりむけていないか、鼻周辺に皮膚炎を起こしていないかなども確認してあげてください。
そして、身体を触るようにし、熱が出ていないか、脱水症状は出ていないかなども一緒に確認するようにしましょう。
鼻が乾いていないかの観察も大切ですが、愛猫に健康で居続けてもらうためには鼻以外も同時にチェックするようにしてください。
健康状態が良い猫ちゃんは基本的に、活発でたくさん遊ぶ、よく食べてよく眠る、規則正しい便をする、毛艶も良くてイキイキとしています。
体調不良のサインとしては、ぐったりしていて元気がない、足元がおぼつかない、呼吸が普段より速い、下痢や嘔吐などの消化器症状が出ている、急激な体重の減少、異常な体臭などが挙げられます。
猫は痛みや不調があっても飼い主に訴えるようなことをせず、極力動かないで回復するのを待つといった我慢強い動物です。
そのようなことも念頭に入れつつ、飼い主さんは愛猫の健康サインを見逃さないようにしましょう。
まとめ

猫の鼻は普段湿っているものですが、乾いていると気付いたときは病気を疑う飼い主さんも少なくないはずです。
しかし、乾燥が一時的なものであれば、自律神経の働きによって起こる生理現象となるため、不安視する必要はありませんが、何かしらの病気などを患っていて乾燥している場合は注意が必要となります。
このようなことからも普段から愛猫の健康状態を把握しておかなくてはいけませんし、少しでも別の異変が見受けられる場合には、迅速に行動ができるようにしておきたいものですよね。
愛猫を守ってあげられるのは飼い主さんだけとなるため、体調不良のサインを見逃さないようにしながら、健康で居続けてもらうように努めていきましょう。