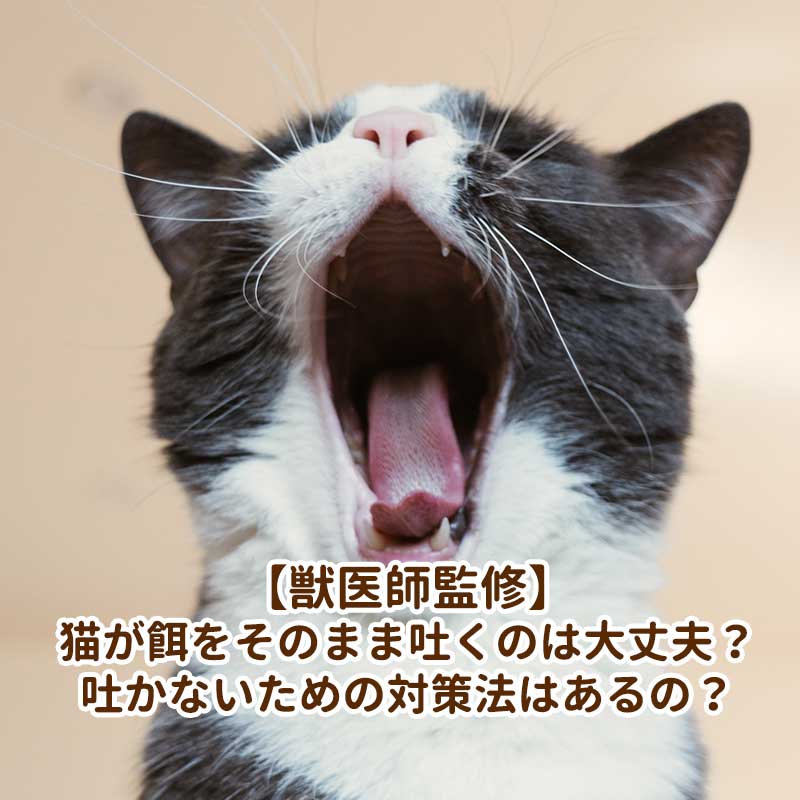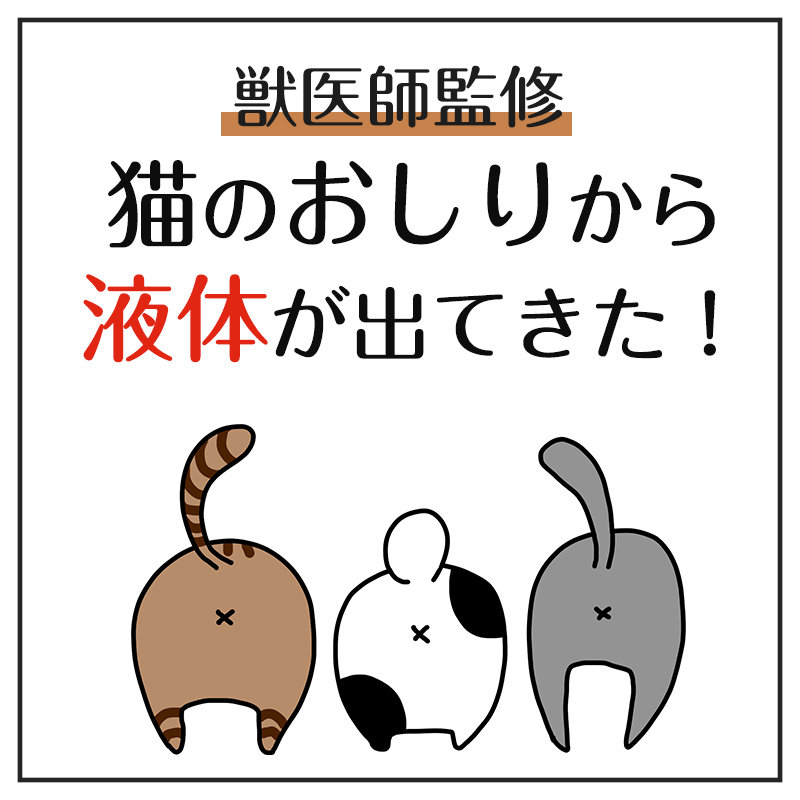猫の水頭症とはどんな病気?

脊髄動物の脳は頭蓋骨の中で脳脊髄液といった液体の中に浮き、脳から連続している脊髄は中枢神経を構成する器官となりますが、脊柱内で脳脊髄液の中に浮かんでいる状態となります。
脳脊髄液は脳室内にある脈絡叢(みゃくらくそう)といった器官で産生されており、頭蓋や脊柱内の空間を満たしてくれています。
しかし、この脳脊髄液が過剰に貯留したり流れに問題が生じたりすると脳が圧迫され、脳室が拡張すると脳が正常に機能しなくなり、もとの構造が保てなくなってしまう疾患を「水頭症(すいとうしょう)」と呼びます。
猫の水頭症は犬と比べるとまれとは言われていますが、さまざまな障害が出るため注意が必要な病気と言えるでしょう。
水頭症の主な症状
猫が水頭症を患っている場合は、以下のような症状が見られることがあります。
・元気消失
・食欲異常
・視力障害
・ふらついてうまく歩けない
・一方向に転ぶ(回転する)
・性格が変わる
・けいれん
・頭部が丸くふくらむようになる
起きていても常にぼーっとして元気がなく、通常の猫よりも眠っている時間が長くなるといった症状や、ふらついてうまく歩けずに転んでしまう、物にぶつかる、壁に沿って歩くなどの症状がよくみられます。
食欲も低下しあまり食べなくなってしまう子も居れば、過食気味になってしまう子も居るため、食欲異常といった症状にも注意しておかなければいけません。
神経症状が出ることによって性格が攻撃的になってしまう、けいれん発作が起きるなどの症状が見られるケースもあります。
また、水頭症は脳が圧迫されて障害が起きる病気のため、頭部にボールやドーム状のような球体ラインが現れるようになります。
頭が丸くなるのと同時に斜視が見られるケースもあるため、見た目にも注意しておくべき疾患と言えるでしょう。
猫の水頭症の原因
厄介な病気となる猫の水頭症ですが、どのような原因によって発症するかも気になるところですよね。
水頭症を患う原因は、主に以下のような要因が考えられています。
◆先天性
猫の水頭症は先天性といった遺伝によるものが多く、もともと脳や脳脊髄液の形成、流れなどに異常が出る場合があります。
遺伝で水頭症を発症する場合には、多くは1歳未満で発症する確率が高いため、成長過程で気になる症状が出ている場合には、早急に動物病院を受診して原因を探るようにしましょう。
◆後天性
後天的要因によっても水頭症が発症することがあるため、すべての猫ちゃんに注意が必要となります。
後天性の要因については脳腫瘍や脳内出血、髄膜炎から併発することがありますが、そのほかにも外傷によって脳脊髄液の流れに異常が出たり、循環経路が断たれて産生が過剰になったりすると発症リスクが高まることも。
また、伝染性腹膜炎(FIP)といったウイルスの感染により、水頭症を引き起こす可能性もあるため、注意が必要と言えるでしょう。
◆どの猫種がなりやすいのか
水頭症を好発しやすい猫種と言われているのが、純血種のシャム猫です。
先天的な要因で水頭症を発症するリスクが高いため、シャムと一緒に暮らしたいと考えている方は、このことをしっかり認識した上でお迎えするようにしてください。
猫の水頭症の治療法

愛猫が水頭症を発症していた場合、どのような治療が行われていくのか気になる飼い主さんも多いと思いますが、水頭症の治療法は症状の軽重や安定度によって治療法がかわります。
水頭症の検査はCT検査やMRI検査、神経学的検査、頭部の超音波検査などを行って診断しますが、その際に診断された症状に合った治療をすすめていくことがほとんどです。
◆薬物療法
水頭症は根治の難しい病気ではありますが、症状が軽度で状態も比較的安定しているようであれば、薬物療法といった内科的治療が行われることが一般的です。
脳圧を下げるために副腎皮質ホルモン薬(ステロイド剤)、降圧利尿薬などを投与し、対処的な治療を行っていきます。
てんかんなどの発作が起きる場合には、発作の回数が多ければ抗てんかん薬などを用いて治療を行っていくようです。
このような治療をしながら経過をみていきますが、薬物療法で症状の改善が見られない、症状の悪化や副作用などが認められた場合には、外科的治療が必要となります。
◆外科手術
外科的治療とは手術のことを指しますが、水頭症では「V-Pシャント(脳室-腹腔シャント)」といった手術が一般的となります。
V-Pシャント術は脳室から腹腔にかけて医療用の管でつなぎ、脳脊髄液が脳内に過剰に溜まらないようにするため、余分な脳脊髄液を腹腔内に排出するといった手術となっています。
猫への負担も大きくどの猫ちゃんにもできる手術ではないため、さまざまな検査結果や体力などを含めて判断し、手術に耐えられるかどうかを検討するようです。
術後は対処療法に切り替えて経過をみていくことが一般的となるため、獣医師さんと協力しながら術後の経過を見守っていきましょう。
猫の水頭症と付き合うためのケア方法
愛猫が水頭症を患ってしまった場合、継続的な治療が必要となりますが、一緒に暮らしていく上で飼い主さんはどんなケアをしてあげれば良いのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
さまざまな症状が出るからこそ、少しでも日常生活では負担をかけたくないですし、辛い中でも頑張る愛猫に長生きしてほしいものですよね。
飼い主さんは水頭症を患う愛猫のために、どんなケアを心掛けてあげるべきなのでしょうか。
◆日常生活でできること
水頭症の猫と一緒に暮らしていく上で、生活していく環境を見直す必要があると言えるでしょう。
神経症状や視覚障害が出ている場合は、室内で猫がケガをしそうな物はなるべく片付けるようにし、室内の段差をなくしつつ角のある家具はクッション材を用いるなどをして、ぶつかってもケガをしないような配慮もしなくてはいけません。
また、重症化して寝たきりになってしまった猫ちゃんには、長時間寝ていても疲れないような寝床を提供するようにし、手足の麻痺などで床ずれができてしまうようであれば、定期的に負担がかからないように向きを変えてあげる必要があります。
トイレも粗相が続くようであればおむつを着用させ、定期的な交換を怠らないようにしつつ、全身を優しくブラッシングする、汚れた部位は拭き取ってあげるなどをして、常に清潔を保ってあげられるように意識してください。
大切なのは愛猫が何を感じて何を求めているのかを察知できるかといった、信頼関係です。
日々のコミュニケーションを欠かさないようにし、愛猫が何を求めているのかを読み取ってあげるようにしましょう。
◆食事や水分補給に気を配る
毎日の食事や水分補強にも気を配る必要があるため、過食気味の子の場合は1日に必要な摂取カロリー内に食事内容を収めるように努める、食欲が落ちている子の場合は食べてくれるフードを探す、柔らかくして喉越しをよくする、高カロリーの療法食を与えるなど、試行錯誤しながら栄養不足に陥らないような手助けが必要となります。
お水も自ら飲めないようであれば、水分の多いフードを与える、シリンジやスポイトなどを用いた、強制給水も視野に入れておかなければいけません。
◆定期的な診察と投薬管理の大切さ
自由が利かなくなる症状が多くでる水頭症ですが、不自由な身体に負担をかけることを懸念して、動物病院へ連れて行くのを迷ってしまう飼い主さんは少なくないはずです。
しかし、水頭症といった病気は時間とともに状況が変化していく病気でもあるため、定期的な診察が不可欠となります。
定期的な治療だけでなく獣医師さんからのアドバイスを得ることにより、飼い主さん自身の心の負担への軽減が期待できますよね。
そして処方された薬は医師の指示通りに投薬しないと、病状が悪化してさらにひどい症状が出る可能性もあるため、飼い主さんの判断で減らしたり増やしたりすることは絶対にやめてください。
まとめ

猫には発症例が少ない病気と言われている水頭症ですが、絶対にかかることのないと言い切れる疾患ではないため、猫と一緒に暮らす以上注意をしておくべき病気と言えますよね。
ほとんどの場合は先天性といった遺伝が原因となりますが、後天性の場合はさまざまな要因が考えられるため、危険を事前に取り除くような生活環境づくりも大切です。
そして、水頭症は自然治癒する病気ではないため、定期的な健康診断は怠らないようにし、少しでも愛猫に水頭症のような症状が見られた場合には、様子をみるようなことはせずに早急に動物病院を受診するようにしましょう。