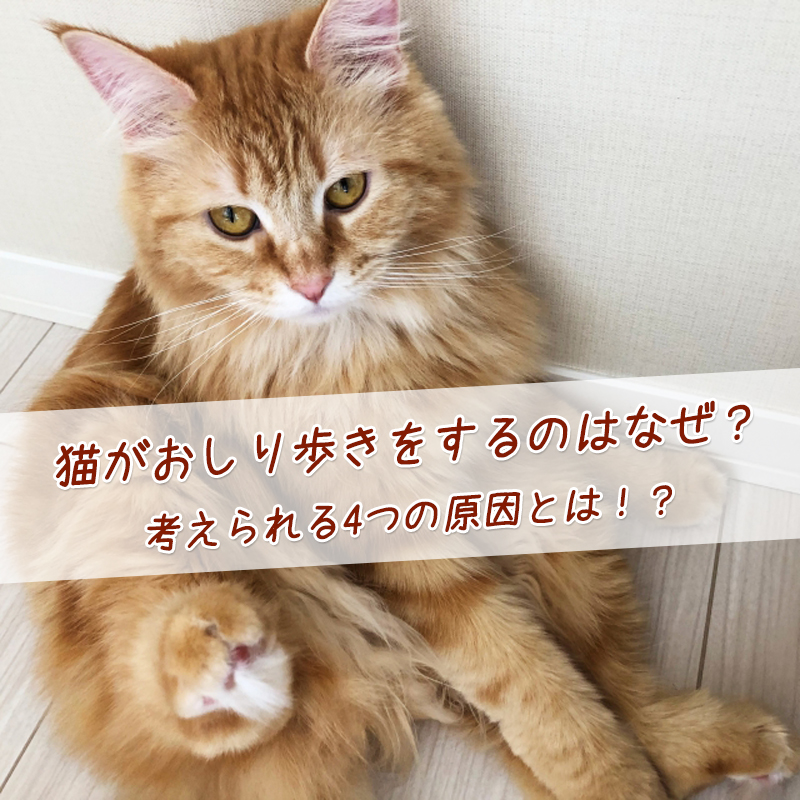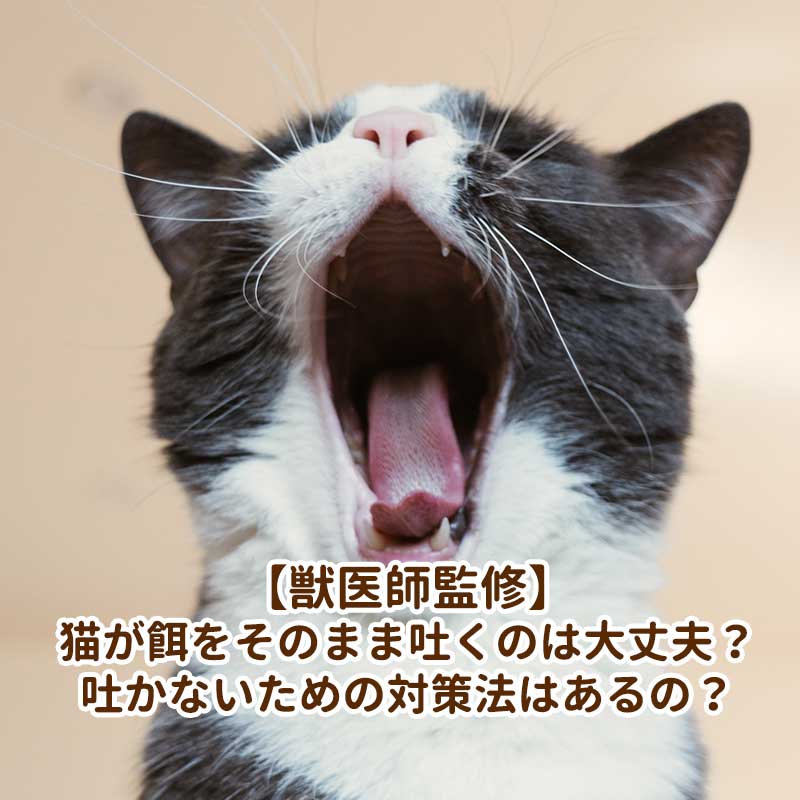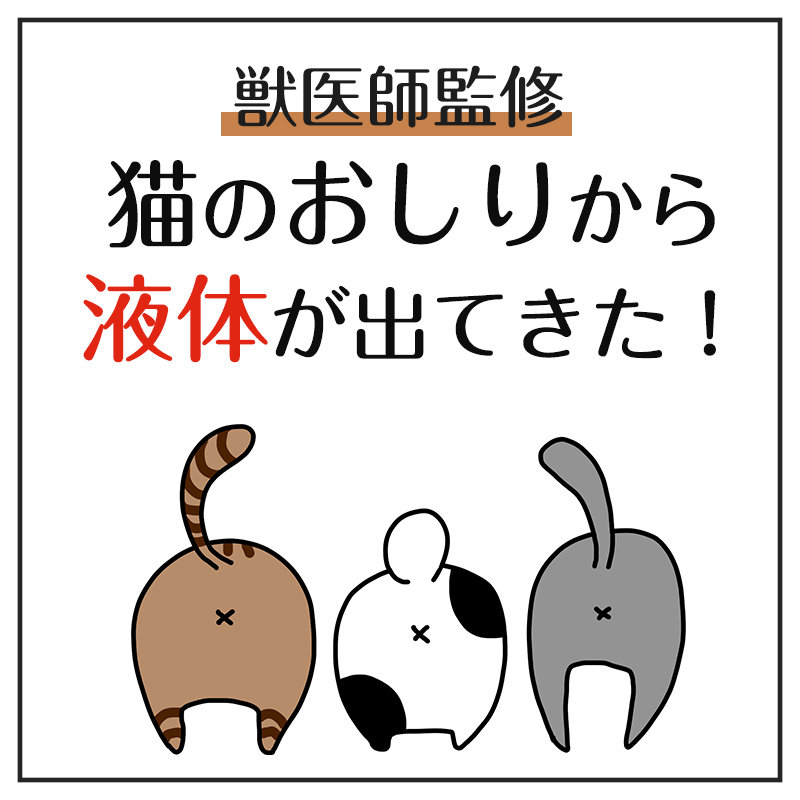猫がおしり歩きをするのはなぜ?

猫は見た目だけでなく、すべての動作がかわいさに溢れている動物ではありますが、ときどき飼い主さんもビックリするような行動をすることがありますよね。
飼い主さんの中には、愛猫がおしりを床に擦りつけながら、前足の力によって前に進むといった、不思議な歩き方をしている姿を見たことのある方もいらっしゃることでしょう。
表情は真剣そのものなので、余計に面白みが増しますが、きっと猫にとっては何かしらの理由があり、仕方なくこのような歩きになってしまったのかもしれませんよね。
何かしらの理由があるのであれば、おしり歩きはかわいいだけの仕草ではなく、対策が必要になってくるはずですので、まずは猫がおしり歩きをする原因から探っていきましょう。
猫がおしり歩きをしてる原因
愛猫が床におしりを擦りつけ、その体勢のまま前進する姿を目撃した場合、なかなか見慣れない姿に衝撃を受ける飼い主さんは多いはずです。
一見ユーモラスな姿なので、微笑ましい気持ちで傍観してしまうところですが、すべての猫ちゃんがこのような歩き方をするわけではないので、なぜこのような歩き方をするのか、飼い主さんが原因を探って解決する必要がありますよね。
猫がおしり歩きをする原因として考えられるのは、おしりにまつわる以下のような現象が挙げられます。
◆便秘
猫にとっては排泄の条件などを知る由もないので、お腹に何かしらの違和感を覚えればトイレに行くはずですが、そこで思ったように便が出し切れなかったり、力んでもうまく排便できずにキレが悪かったりすれば、お腹のモヤモヤは残ったままになってしまいますよね。
とくに便秘のような出したいのに出ないといったメカニズムは、猫には理解できませんし、どうにか排泄させようとした結果、おしり歩きをしてしまう子が居たとしても不思議ではありません。
それぐらい排泄は猫にとって気持ちや行動を左右しますので、たかが便秘として受け取らない方が良いでしょう。
◆下痢・軟便
便秘だけでなく、下痢や軟便の際にも猫はおしり歩きをすることがよくあります。
普段問題なく排便ができている猫ちゃんであれば、何かしらの理由によって便が柔らかくなり、肛門付近の被毛に排出した便が張り付けば、不快感が拭えずどうにか拭き取りたいと思うはずですよね。
また、飼い主さんの髪の毛を食べてしまった場合や、猫草やひも状のものを食べた場合などは、便と絡まって繋がったまま排出されることがあるので、ぶら下がった状態に気付いて焦る気持ちが高まれば、必死に引き離そうとするはずです。
その結果としておしり歩きといった特徴的な行動をとりますので、便の状態は常に把握しておくに越したことはありません。
◆肛門嚢の目詰まり
猫の肛門には犬と同様に、強い臭いを放つ左右一対の「肛門嚢(こうもんのう)」があります。
別名「肛門腺」とも呼ばれる肛門嚢は袋状になっているので、その中にはアポクリン腺や皮脂腺から排出される分泌液が蓄積されますが、何かしらの原因により肛門嚢が目詰まりを起こせば、猫はその違和感から解放されたいがために、おしり歩きをするようになります。
基本的には溜まった分泌物は便と一緒に排出されますが、猫ちゃんによっては生まれつき目詰まりを起こしやすい子や、便が常に柔らかい子が居ますので、排泄で力む際に刺激が足りず、そのまま目詰まりを起こすことがあるようです。
◆肛門嚢炎
愛猫のおしり歩きがたまにではなく、毎日のように頻繁に見られる場合は、「肛門嚢炎」を発症している可能性があります。
肛門嚢炎は肛門腺の目詰まりや、細菌に感染することにより炎症を起こしますので、分泌物(膿)が貯留すれば肛門部分に痛痒感といった症状が現れます。
症状が軽いうちは痒みが出る程度なので、おしり歩きをして気を紛らわそうとしますが、症状が悪化すれば痛みが増し、肛門付近の皮膚が自壊して穴が空いたり、出血したりすることもあるので、飼い主さん自身がびっくりしてしまうことでしょう。
放っておくと病気になる?

猫がおしり歩きをたまにするぐらいであれば、そこまで心配しなくても平気と考える飼い主さんは多いと思いますが、猫のおしり歩きは何かしらの異常のサインです。
一度でもそのような行動をとった猫ちゃんは、また同じ違和感を覚えれば、おしり歩きが癖になって何度も繰り返しますし、頻度が多くなれば肛門への負担も大きくなっていきますよね。
肛門付近の皮膚はとてもデリケートで繊細となり、床の凹凸などで傷がつけば、さらに症状を悪化させてしまうことも否めません。
そのまま放っておけば肛門嚢の目詰まりや、肛門嚢炎だけでなく広範囲での皮膚炎、痛みによってオシッコを我慢する膀胱炎など、ほかの病気が併発することもあるので注意が必要です。
できることならおしり歩きを目撃した際に、飼い主さんがしっかりと原因追及をし、肛門嚢に問題がありそうな場合には早急に動物病院を受診し、適切な治療を行うことをおすすめします。
肛門絞りをした方が良い?
もし猫のおしり歩きの原因が肛門嚢にある場合は、溜まった分泌液を排出させる必要があります。
基本的には排便時に圧迫されて便と一緒に排出されますが、猫ちゃんによっては自然に排出されなかったり、もともと体質的に溜まりやすかったりする子も居るので、そのような場合には定期的なケアが必要と言えるでしょう。
猫の肛門嚢は肛門を中心に、時計の4時と8時を指す位置に一対ずつ在りますので、親指と人差し指をその下に起き、少し力を込めて指を上に押し上げるようにして分泌液を排出させます。
肛門嚢に溜まった分泌液は、ドロッとしていたり水分量が多かったりと、個体によってさまざまです。
たくさん溜まっている猫ちゃんの場合、勢いよく飛び出すこともあるので、飼い主さんは汚れても良い格好で手袋をして行うか、お風呂場などで肛門絞りを行うと良いでしょう。
猫ちゃんの中には無理矢理押さえつけられて、肛門付近を触られないようにと全力で阻止する子も多く、絞ることが難しい場合には、動物病院で絞ってもらうなどの選択肢も頭に入れておくと安心です。
動物病院によって肛門腺絞りの金額は異なりますが、平均的に1,000~3,000円前後で処置してもらえますので、かかりつけの動物病院に確認してみるようにしましょう。
猫がおしり歩きをした時の対処法
猫にとっておしりから出る分泌液は、情報交換のために必要不可欠となるので、必ずなくてはならない分泌物となっています。
猫ちゃんの中には興奮したり緊張したりするときにも、分泌液が出てしまう子も居ますし、それもその子の個性として受け止めてあげることが一番です。
もちろん個性だからといって放置することは望ましくありませんが、便秘や軟便の場合は食事内容を見直し、腸内環境を整えるような工夫をしてあげてください。
肛門嚢が目詰まりを起こしているのであれば、肛門腺絞りを定期的に行うなどをして、分泌液が溜まらないように心掛けてあげましょう。
肛門嚢炎を起こしている場合は、症状を悪化させないためにも、動物病院を受診して適切な治療を行いつつ、獣医さんに相談して肛門腺絞りのやり方を教わってみるのもおすすめです。
猫のおしり歩きは生理現象となりますので、飼い主さんがしつけを行ったところでやめさせることはできませんし、治らないからといって叱りつけるのはご法度となります。
愛猫がおしり歩きをした際に飼い主さんがまずやるべきことは、愛猫のおしり付近をキレイにしてあげ、床などに付着した分泌液の臭いが残らないように、しっかりと掃除をして清潔を心掛けることです。
臭いが残ってしまえば、同じ場所にマーキングや粗相をしてしまうこともありますし、キレイを保つことによって、再度おしり歩きの痕跡を見つけやすくなりますので、愛猫の健康管理がしやすくなります。
まとめ
基本的に猫はキレイ好きな動物で便のキレが良い上に、セルフグルーミングで肛門付近の清潔を保ちますので、おしり歩きとは無縁と考えて問題ありません。
何かしらの原因によりおしり歩きをする場合は、猫にとってよっぽどの緊急事態となり、不快感が残っているサインとなるので、早急な対策が必要と言えるでしょう。
飼い主さんはおしり歩きの原因をしっかりと追究して、癖にならないような対策を心掛けてあげなくてはいけませんよね。
猫ちゃん自身もおしり歩きをやりたくてやっているわけではないので、何度も繰り返せばストレスが溜まり、別の問題行動が出てくる可能性も否めません。
愛猫のストレスを軽減させる目的でも、おしり歩きを目撃した際には適切な対処をして、心身共に健康でキレイな状態を維持できるように手助けしてあげてくださいね。
– おすすめ記事 –
| ・猫のおしりが汚い原因は?下痢うんちの拭き方や肛門腺絞りの方法について |
| ・猫がお尻ポンポン好きな理由3つ!ポンポンする効果や注意点は? |
| ・猫のしっぽが気持ちを表すって本当?尻尾が膨らむ理由と気持ちを詳しく! |
| ・猫に必要なお手入れ総まとめ!手順と頻度を詳細に |