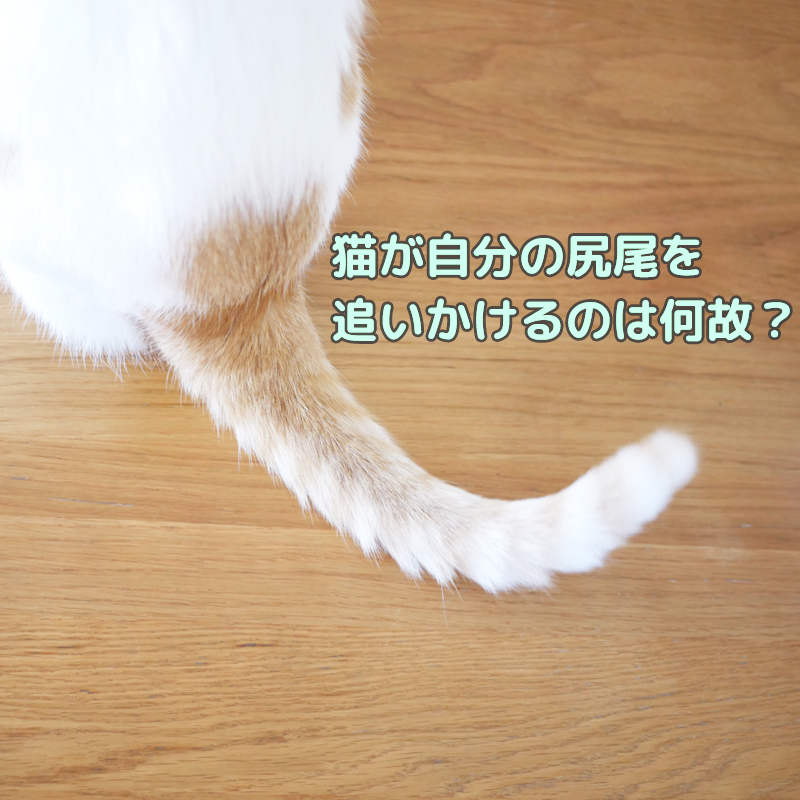【掲載:2017.06.11 最終更新:2025.04.15】
猫がご飯を残す理由は?
猫の食欲にはムラがあるのか、ご飯をちょっとだけ残すことも多いです。
初めは喜んで食べていたのに、途中でご飯を残すとなんだか心配になってきますよね。
猫がご飯を残す理由として、以下のようなものがあるようです。
②もう食欲が満たされて満足したから
③年齢的なものが原因となることも…
④ほかのエサを食べたがっている
⑤いつもと違う味に困惑している
⑥環境の変化が原因になっていることも
◆その1:野生のときの特徴が本能として残っている

今や猫ブームで飼い猫としての頭数も増えている猫ですが、かつては厳しい自然界を生き抜くためにワイルドな野生生活をしていました。
ご飯となる獲物を見つければ自分の力だけで捕獲して、毎日自分で食べ物を確保しなければならないのですが、獲物が見つからないときもありますよね。
それに、せっかく見つけた獲物がライバルに奪われてしまうことも。
「いつでも何度でも食べることができる」という飼い猫のようには生きられないのが野生猫なのです。
そこでエサとして捕獲できた獲物は、一度にすべて食べません。それを食べてしまうと、次の食事がいつできるか分からないからです。
少し食べて残す、残ったものはまた食べて少し残すというように、何度かに分けて食べていたようです。
こんな野生時代の習性が今も本能として残っています。
もし、愛猫がご飯を食べているときにちょっと残す傾向にあるなら、もしかして「後で食べよう!」とキープしているつもりなのかもしれませんよ。
◆その2:加齢のため
猫はそもそも満腹過ぎる食事量は必要としない小食系の動物です。これも野性時代の体質と関係があり、お腹いっぱいにエサを食べてしまうと動きにくいからなのでしょう。
せっかく見つけた獲物がいても、満腹過ぎて動きが鈍くなると獲物を追いかけて捕獲することが難しいものですよね。
狩りでスムーズに動くために、自分がお腹いっぱいという量の限度を知っているので、結構すぐに満足してしまいます。
ただ、子猫のときにはその限界を知らずにたくさん食べてしまうことがあります。そのため、食べ過ぎてしまい胃への負担が大きく、後から吐いてしまう猫もいるのです。
◆その3:加齢のため
人間と同じように、動物も年齢と共に食べられる量がだんだん減っていきます。
すると、若いときに食べていた頃と同じ量のご飯が、高齢の猫には「多すぎて無理」ということもあります。
また、お口の中や内臓など、体全体に高齢化が起きています。噛む力も衰えるので、自然に食欲もなくなります。
たくさん食べなくても満腹サインが体から出るので、自分にとって量が多ければ少し残すこともあります。
◆その4:ほかのご飯を食べたがっている

愛猫がご飯を残すため「このご飯が嫌いなのかな?」とほかの種類のご飯やおやつをあげる飼い主さんもいるかもしれません。
猫にとっては単に気まぐれで残すだけの行動だったとしても、美味しいご飯やおやつがもらえると喜ぶでしょう。そこで「食べ残す=おやつがもらえる、他の美味しいご飯がもらえる」と覚えてしまいます。
例えば、いつもはドライタイプのキャットフードを食べていた猫が残すことによってウェットタイプのものをもらえたとします。猫は結構グルメなので、舌で美味しさを察知します。
ドライフードとウェットフードは食べたときの感覚が違いますよね。舌がそれを覚えていて、恋しくなるのでしょう。
食べ残すと「美味しいご飯がもらえるんだな」と学習して、わざと残す行動を見せ「この前の美味しいご飯をちょうだい」と無言の要求をしてくることもあるようです。
◆その5:いつもと違う味に困惑している
新しいご飯に切り替えたら残すようになることもあります。
やはり、猫の繊細な舌が味と感触を覚えているので、いきなり全く違うご飯に変えると気になって残すこともあるのでしょう。
フードの種類を変えるときには、前のフードに少しずつ混ぜて1週間くらいかけて切り替えるようにすると良いでしょう。
また、いつものフードなのに残す場合もあるかもしれません。食べ慣れた味を残すのは、フードの鮮度が落ちているからかもしれません。劣化してニオイがきつくなっていないかチェックしてみてくださいね。
◆その6:環境の変化が原因になっていることも
猫はデリケートな動物です。ちょっとした環境の変化も感じ取り、気持ちに表れます。
・食器を変えたら残すケース
いつも使っている食器が古くなったから変えてみよう…と、気分転換のつもりで猫の食器を変えたら食べ残すようになることもあります。
「いつもの食器じゃない!」と察知するのでしょう。ふだん使い慣れている食器に戻した方がいいかもしれませんね。
・食べる位置が違うことが気になるケース
食事をさせる位置が違うと敏感に反応することもあります。
「場所が違う。食べづらい」というアピールで残すこともあるようです。そんなときには、食べる位置を戻してみましょう。もしかして、再び食べるかもしれません。
・旅行、引っ越し、新しい飼い主など大きい変化があるケース
旅行や引越しなど見知らぬ環境では猫は落ち着かなくなります。気まぐれでマイペースに見える猫たちも、知らず知らずのうちにストレスを溜めこんでいます。
お腹がすいているのに、緊張が続いたせいでご飯を残すこともあります。
・大好きな飼い主さんが留守で寂しいケース
ツンデレな性格が魅力な猫ですが、愛情を持って接してくれる飼い主さんのことは大好きです。なかには犬のように飼い主さんのそばをついて回る猫もいるでしょう。
いつも一緒にいる飼い主さんが、出張や入院で留守にするなどいつもより長く不在になると寂しさから食欲がおちます。そんなときには、エサも残す傾向にあるようです。
繊細な心を持つ猫は、何らかの環境の変化で恐怖を感じたり、興奮したり、落ち着かなくなったりとストレスを溜めやすいです。ちょっと残す程度ならいいですが、あまりにも食べないケースなら病院に連れていくなど何らかの対策をした方がいいでしょう。
猫の食事の与え方は?
飼い猫の場合、自分で食事を準備することができないので、飼い主さんが食事管理をしなければなりません。間違った食事の与え方で、猫が不健康になってしまうことも。
年齢によっても違った食事方法が必要になります。どんな食事の与え方がいいのでしょうか。
◆年齢に合せたフードを準備する
たくさん食べて欲しいからと、どんな年齢の猫にも同じ量を与えるのは間違いです。
年齢に応じて1日に必要なエネルギー量があります。「室内で暮らす猫」「運動量が少ない猫」「体重が増えすぎている猫」など個体差があるので、愛猫に合ったフードを準備し、適切な量を食べさせてください。
猫の習性から、ムラ食いをするとも言われているものの、なかには「いつでも食欲がある」という猫もいます。「食べるから…」と与え過ぎると肥満にもなってしまいます。
それに、高齢の猫にエネルギー量が多い若い猫用のフードをあげると太ってしまいます。年齢に合ったものを与えて食事管理をしっかり行うことが愛猫の健康への近道です。
また、多頭飼いをしている場合、一度にまとめてご飯をあげないようにしましょう。一つの食器にすべての猫の分のエサをまとめてあげると、食べる量に偏りが出てしまいます。
こっちの子はたくさん食べたのに、こっちの子は栄養不足…なんてことにもなりかねません。
年齢によって必要なエネルギーや量、回数も違うので、それぞれの猫の食器を準備してライフステージに合った食事量・回数を管理してあげてくださいね。
◆猫の胃への配慮で回数をこまめにする
1日の食事の量を1日1回だけ与えると、猫の胃への負担が大きいです。たった1回の食事では食事量が多く、食べ残すことに繋がります。
それに、空腹の時間も長くなるのです。1日の適切な食事量を数回に分けて食べさせましょう。
一般的に子猫の場合は1日3~4回、成猫の場合は1日2回、高齢猫の場合は1日3~4回が良いと言われています。
特に、高齢猫はお口の環境も変化し始め、噛む力も弱くなります。1回の食事量が多いとかなり負担と感じてしまいます。
なるべく食べ残す量を減らすには、1回あたりの食事量を少なくするといいでしょう。また、噛む力も弱いので小粒で柔らかなフードをあげるのもおすすめです。
食べ残しのご飯、また後で食べさせてもOK?

ムラ食いの猫たち。少し残すこともあるでしょう。「後で食べるんだな」と思って食べ残しのフードが入ったまま置いておくのは、あまりよくありません。
一度食器に入れて猫が口をつけたフードは、時間が経つとどんどん劣化していきます。猫の唾液が付着しているため、残したエサは少しずつ雑菌が増えていきます。冷蔵庫に入れても同じことです。
劣化が進んだエサはニオイが変わるので、猫も気づきやすいです。「味が違う」とますます食べないこともあります。また、食べ残したフードに新しいフードを混ぜるのも衛生的にはNGです。
最も良いのは、食べ残しがないように1回に与える量を調節することです。もし残ってしまったら、置いたままにせずにすぐに片付けましょう。
特に、夏など気温が高い時期にはエサも傷みやすく、それが原因で猫の体調に影響が出ることもあります。飼い主さんが管理していくように気をつけましょう。
まったく食べない場合は病気が心配!
食べ残す場合に、病気が原因でほとんど食べないこともあります。
・吐いたり、下痢をしたりしている
・元気がない
・ご飯にまったく手をつけない
・全く食べない日が1~2日続く
このように、何も食べない日が続いたり、食欲不振以外にも何らかの病的な症状が見られるときには注意が必要です。
何かしらの病気が原因で食べないこともあるので、動物病院に行って獣医に相談してみることをおすすめします。
まとめ
基本的にネコたべと言われている猫の食べ残しは、野生の名残でもあります。「猫はムラ食いするんだな」と理解しておくといいですね。
少し残す程度なら、あまり気にすることはありません。ちょっとした気まぐれな気持ちなのかもしれません。食べ残しをしないように、フードや食事回数、環境などで工夫をしてあげるといいでしょう。
猫にとってたくさんの量を一回に与えることは体に良いことではありません。猫の食事管理ができるのは、飼い主さんだけです。愛猫と長く幸せに暮らすため、猫に無理をさせない食事タイムを心がけましょう。
– おすすめ記事 –
| ・猫の好き嫌いを徹底調査!食生活を見直そう |
| ・老猫が食事を食べない時にできる4つの工夫!介護の方法は? |
| ・猫のご飯の種類やあげ方(時間・回数)は?食べ過ぎる猫の対策はこれ! |
| ・夏バテかな?ご飯を食べてくれない猫ちゃんのためにできること |