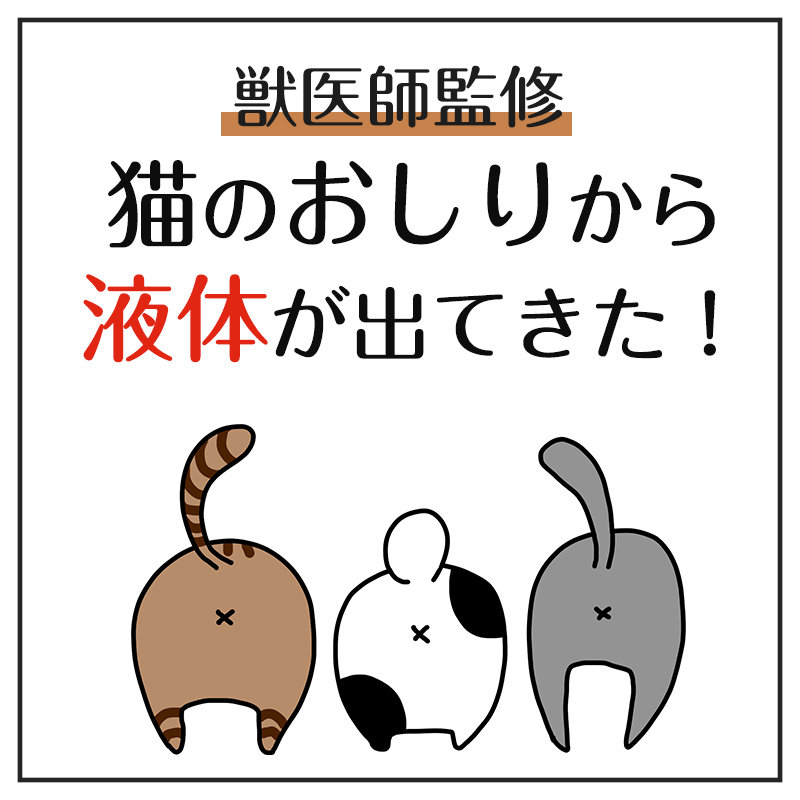1.猫の耳血腫ってどんな病気?
2.耳血腫の症状
2-1.耳介が膨らむ
2-2.耳を気にして掻いたり頭を振ったりする
2-3.耳が垂れ下がる
猫の耳血腫ってどんな病気?

猫の耳の内側となる耳介(じかい)に、血液やさらさらとした透明な分泌液となる漿液(しょうえき)が溜まって、血種ができる病気を「耳血腫(じけっしゅ)」と呼びます。
血液や漿液が溜まって膨らむため、風船や二枚貝のような特徴的な見た目となり、愛猫の耳が変形していることに気付いて、慌てて動物病院へ連れて行くケースがほとんどとなるようです。
ここまで症状が悪化する前に気付く飼い主さんが多いこともあり、重症化を防いで早期から治療を開始すれば完治も期待できる病気のため、発症初期ではどのような症状が出やすいのかを知っておく必要があると言えるでしょう。
猫が耳血腫を患った場合、どのような症状が現れるのでしょうか?
耳血腫の症状
猫の耳血腫は発症している猫を見たことのない方であれば、どのような症状が出るのかを知っておくべきですが、代表的な症状は以下の通りとなっています。
◆耳介が膨らむ
耳血腫は人間が患った場合は、「餃子耳」や「柔道耳」などと呼ばれることがありますが、人の耳の形状的にそのような見た目になりますが、猫の場合は人よりも耳介の面積が広いため、パンパンに膨らんだ風船のような形状になります。
血管や軟骨のある耳介に血液や漿液などが溜まるため、見た目は空気を含んだかのような形状をしていますが、腫れた耳に触れてみるとぶよぶよとした波動感があり、異常事態であることがうかがえることでしょう。
耳血腫自体に強い痛みは感じないものの、液体でパンパンに膨らんだ耳の重さに違和感を覚えているはずのため、早期に発見してあげることが重要となってきます。
◆耳を気にして掻いたり頭を振ったりする
耳が重くなることによって違和感を覚え、気になって耳を掻いたり頭を振ったりする子も多くいるようです。
この症状は原因によっては耳血腫ができる前から見られることもあるため、愛猫の異変にいち早く気付いてあげられるかも、重要なポイントとなってきますよね。
痛みがあまりなかったとしても違和感があれば気になるのは当然ですし、前足や後足で引っ掻いてしまえば、新たに傷を作ってさらに症状が悪化する可能性も否めないため、早急の治療が必要とも言えるでしょう。
◆耳が垂れ下がる
耳介に液体が溜まって腫れるということは、その分重みを感じますし、じっとしていたとしても重みによって耳が徐々に垂れ下がってきます。
重さを感じれば煩わしさを覚えますし、耳で平衡感覚や体温調節などの役割を担っている猫にとっては、それらの機能を十分に発揮できないこともあり、元気を徐々に消失していく猫ちゃんも少なくないはずです。
猫の耳血腫は見た目で分かりやすい症状が現れやすいため、日頃から愛猫のことをよく観察し、異常がないかの確認を怠らないようにしてあげてください。
耳血腫になる原因
猫の耳血腫はまだまだ原因が解明されていない部分もありますが、物理的な刺激によって血管が破綻することで発症するケースが多い、と言われています。
猫が感じやすい物理的な刺激は以下の通りとなり、これらの原因が発症を促している可能性が高いと考えられています。
◆外耳炎
猫が耳血腫を発症する原因としてもっとも多く考えられているのは、外耳炎を患っていることによる発症だと言われています。
外耳炎は細菌や真菌といったカビなどの繁殖や、耳ダニといった寄生虫の繁殖、アレルゲンによる過敏症、異物混入による腫瘍の発生などが考えられています。
外耳炎を患うと耳に強い痒みや違和感を覚えるため、前足や後足で激しく引っ掻いたり頭を大きく振ったりすることによって、違和感を拭おうとしますが、これらの行為が耳血腫を併発させる原因となるため、できることならこれらの症状が見られるうちに早期発見してあげたいものですよね。
外耳炎を患ったまま放置してしまえば、違和感を拭うための行為によって耳介がさらに傷付くことにより、耳介内の軟骨が揺さぶられ、内出血といった損傷を起こして腫瘍となっていくことでしょう。
耳を引っ掻いたり頭を振ったりする以外にも、黒い耳垢が大量に出る、耳の中から悪臭がする、耳の穴周辺の皮膚が赤く腫れているなどの症状が見られたときには、耳血腫を併発させないためにも早急の対処を心掛けてあげてください。
◆怪我や猫同士のケンカ
外耳炎のほかには、怪我や猫同士のケンカによって耳血腫を発症することがあります。
耳介に傷口ができればそこからバイ菌(病原体)が侵入し、炎症を起こして血液が集まることによって腫瘍へと変化していくこともあるようです。
このような行為は日常的に見られる行為となるため、猫の飼い主さんは普段から怪我やケンカをしていないかの確認し、もし傷ができていた場合には、そこから二次感染をしないような対策が必要となってくるでしょう。
外耳炎や傷口からの炎症のほかに、何かしらの免疫による仕組みが関係している可能性も懸念されており、このようなことからも猫の耳血腫は、普段から注意しておくべき病気とも考えられているようです。
耳血腫の治療法

猫が耳血腫を患った際の治療法には、さまざまなものが報告されています。
症状に合った治療を行うことが一般的となりますが、主に以下のような治療法が行われることがほとんどです。
●外科治療による切開
●内科治療による薬剤投与
耳血腫の症状が軽度であれば、耳介に注射器を刺して溜まった液体を取り除くといった治療を行っていきます。
命にかかわる病気ではないものの、再発を繰り返す病気となるため、何度かの通院治療が必要となることも多く、猫ちゃんにとってはとても辛い病気であることがうかがえますよね。
重度の場合は患部を切開し、溜まった液体を排出させた後に耳の変形を抑えるため、耳介の内側と外側を細かく縫合していきます。
耳血腫の治療は基本的に内容液を採取することが重要となりますが、再発が高いことからも根本的な原因や症状に合った治療が優先されます。
炎症を抑えるためのステロイド剤や、ウイルスの増殖を抑えるインターフェロン、化膿を防ぐ抗生物質、ダニを駆除する駆除薬投与などといった、内科治療も並行されることが多いようです。
このように猫の耳血腫はさまざまな治療法があるため、飼い主さん自身もしっかりと獣医師さんの話を聞いて、副作用のリスクや費用対効果についても考えていく必要があるのではないでしょうか。
そして治療を繰り返すにつれて、内容液が抜けたとしても耳の違和感が拭えない猫ちゃんに対しては、物理的な刺激(引っ掻くなど)による再発を防ぐために、エリザベスカラーを用いて経過をみることがほとんどです。
エリザベスカラーは猫を守るためにも必要な処置となりますが、動きが制限されることからも元気消失や食欲が落ちてしまう子も多いため、自宅療養中は飼い主さんがしっかりとサポートをしてあげてください。
根気よく治療を続けていけば、多少耳の変形が見られたとしても完治できる病気となりますし、発症したことを後悔するよりも再発させないことを強く意識し、今後の生活に役立てていきましょう。
耳血腫の予防法
猫の耳血腫は発症時も治療時も見た目が痛々しく、できることなら発症させたくないと考える飼い主さんも多いはずです。
耳血腫はその名の通り耳に血種ができる病気となるため、根本的な原因は全て耳にあるといって良いでしょう。
そのため、愛猫が耳に対して何かしらの違和感を覚えたような行動をとっていた場合は、耳に異常がないかのチェックをしてあげてください。
猫の耳はとても複雑な部位となっており、外観がきれいだったとしても、内部では何かしらの異常を来している可能性も高いため、早めに動物病院を受診することをおすすめします。
そして耳の観察を日常的に行うようにし、耳垢が溜まっていないか、強いニオイがしていないかの確認も怠らないようにしましょう。
飼い主さん自身で耳掃除ができそうであれば定期的に行うようにし、難しい場合は動物病院やペットサロンなどでお願いして、常に清潔を保つことも大切です。
まとめ
頭のてっぺんについている猫の耳は、空気の流れや音に敏感で、小刻みに動く様子を見せてくれますよね。
猫の耳を見ていて癒される方も多いように、猫にとってもとても重要な部位となるため、何かしらの異常が現れた際には、早急に対処をしてあげなくてはいけません。
特に耳血腫といった病気は重度になってしまうと、耳介が大きく変形し、元の可愛らしい状態に戻すことが難しいとされています。
片耳がそのようになってしまえば、元々備わっていた機能が低下してしまいますし、猫自身の生活の質を落とすことにも繋がってしまいますよね。
身体能力や平衡感覚が優れた猫の生態を奪わないためにも、飼い主さんは日頃から愛猫の様子を観察し、少しでも異常が見られればすぐに動物病院へ連れていき、適切な治療を受けさせてあげるようにしましょう。
– おすすめ記事 –
| ・【獣医師監修】猫の耳が赤い時の原因は何?動物病院に連れて行くべきなの? |
| ・【獣医師監修】猫の耳ダニってどんな病気?こんな症状が出ていたら要注意!! |
| ・猫がじゃれあいする理由3つ!喧嘩との見分け方や止め方は? |
| ・猫の耳先にあるリンクスティップって何?どんな役割があるの? |