1.犬のサークルとは
犬のサークルとは

犬を飼ったことがあれば、サークルを利用したことがある方が多いのではないでしょうか。
サークルは天井と床がついていないタイプのもので、四方向のみが囲われているものです。
最近では、ケージと同義語で解釈する方もいますが、厳密にいうとケージは四方向囲われたサークルにさらに天井と床がついた六方向囲われたもののことをいいます。
ちなみに、サークルやケージに似た用途のものでクレートと呼ばれるものがありますが、これは持ち運びができるケージのようなもので、室内のみならず車や動物病院などの移動先でも利用できるものです。
犬の室内飼いにサークルは必要?メリットは?
嬉しいことに犬の室内飼いが当たり前になってきていますが、犬の室内飼いにサークルは必要なのでしょうか。
また、室内でサークルを使用するメリットはどのようなことでしょうか。
◆サークルは必要?
サークルが必要か否かは愛犬の大きさや性格などにより異なるため、一概には言い切れません。
最近では大型犬を中心に完全室内フリーで飼っている方も多くいますので、愛犬の様子を見ながら判断することが大切ですが、一般的にはサークルを利用した方がメリットが多いと考えられています。
◆子犬のうちはサークルを利用
子犬のうちはトイレトレーニングや破壊行為を中心にしつけが出来ていないため、必ずサークル(またはケージ)を利用しましょう。
家具の破損防止のみならず、子犬を危険から守り安心して快適に生活させるためにはサークルやケージの利用が必須です。
◆家具の破壊防止
室内に家具や壊されて困るものなどがある場合、サークルを利用することをおすすめします。
破壊行為などの問題行動を起こさない犬であっても、室内で歩いていたり走っていたりするときに家具を破壊する危険性があり、犬にとっても大変危険です。
階段から落ちた・窓ガラスにあたった・家具で目を傷つけた・コードを噛んで感電したなどの事故は頻繁にありますので、愛犬を事故から守るためにもサークルが役立ちます。
不在にする時間が多い場合は、飼い主さんが犬の様子を見ていられないので特に注意が必要です。
◆誤飲防止に有効
室内には食べ物を中心に犬を魅了するものが数多くあり、誤飲には十分気をつけなければいけません。
食べ物であれば犬にとっての中毒成分が含まれているものもあり、物であればサイズによっては窒息などの原因にもなりえます。
犬が誤飲してしまうと危険なものは室内に本当に多く、動物病院に行っても吐かせることができず内視鏡で取り出さなければいけないことがあり、さらに内視鏡で取り出せない場合は開胸手術が必要になるケースもあります。
◆逃亡リスクを減らすために有効
普段逃亡癖のない犬であっても、室内で花火や雷、工事の音にびっくりしたり、外にいる鳥を追いかけようとしたりと、逃亡する危険性はゼロではありません。
犬がすぐに玄関に行くことができる環境よりも、やはりサークルなどを利用していた方が逃亡リスクは減らせるのではないでしょうか。
◆寝床として活用
犬をサークルに入れてしまうと可哀想な気がしますが、実は犬にとってはサークルやケージなどの孤立した自分だけの空間は快適なものです。
犬は野生で生きていた時代、外敵から身を守るために自分で小さな穴倉を掘って寝床にしていました。
そのため、意外にサークルのような狭い空間が落ち着くことが多く、良質な睡眠時間確保にも効果的です。
長時間ずっとサークルに入れたままにしておくのはもちろんNGですが、適度な運動と気分転換・飼い主さんとの十分なコミュニケーションができていれば、サークルは犬だけの安心できるテリトリー・寝床として、快適なスペースになります。
ケージよりサークルがおすすめ?
最近のサークルは、天井や床部分が別売りで販売されているものも多くありますが、必ず六方向が囲われているケージとは異なり、上から水やご飯を出し入れできたり、掃除が簡単に行えるものが多いのもメリットです。
その他、犬の体の成長に合わせて形を変更・サイズを広げることができたり、サイズが比較的大きなものもあるので中型犬や大型犬の室内の寝床としてもおすすめです。
室内に犬のサークルを置く時の注意点
室内にサークルを置く場合は、犬が快適に過ごせるように配置場所や使用方法などに十分気をつけてあげましょう。
◆直射日光に当たらない場所に配置
直射日光に長時間あたるのは、絶対に避けなければいけません。
サークルに入っている犬は基本的に自分で外に出ることができないため、長時間直射日光にあたると皮膚がんリスクのみならず熱中症で命を落とすなど多くの危険が伴います。
どんなに涼しい季節・涼しい室内であっても、直射日光の当たる場所にサークルを置くのはやめましょう。
◆快適な温度になる場所
暑さに弱い犬がほとんどですので、温度・湿度管理がしやすい場所にサークルを設置するのがおすすめです。
風通しの良い場所や冷房完備のある温度・湿度管理のしやすい部屋で、家族と過ごすことができるリビングに設置してあげるのが理想的です。
◆静かな場所
犬のサークル設置場所はできればリビングがおすすめですが、騒音がするような場所は避けなければいけません。
常に小さな子供が騒いでいる・ほかの同居犬がうるさくしているなど、音のストレスは犬にとってよくありませんので、出入りが頻繁に行われるドア付近もおすすめできません。
犬の性格によっても異なりますが、基本的には静かで犬がリラックスできる場所にサークルを設置してあげましょう。
犬の睡眠の質は人とは異なるため、1日の大半(12~18時間)寝て過ごさなければいけませんので、安心して眠れる配置場所であることが大切です。
◆頻繁に移動しない
一般的に犬は、人が想像する以上に環境の変化に弱い生き物で、頻繁にサークルの位置が変わるとストレスに感じる犬も多くいます。
室内サークルは、毎日眠る寝床であり犬のテリトリーとなる場所なので、出来る限り配置換えはしないように心がけましょう。
◆犬を閉じ込めない
犬を叱るためにサークルに閉じ込めたりするのは絶対にやめましょう。
叱るときにサークルに閉じ込めてしまうと、本来犬にとって安心できる空間である室内サークルが犬にとって嫌な場所になってしまいます。
サークルは犬を閉じ込める場所ではなく、安心して休ませる快適な空間でなければいけません。
犬の室内飼いにおすすめのサークル3選
◆いつでもキレイ!木製お掃除簡単ペット室内サークル

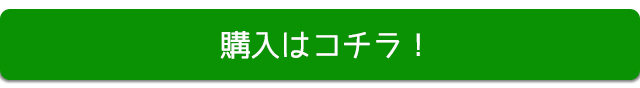
別売りで屋根やサークルを覆うカバーなども販売されてますので、用途に合わせて使い分けることができます。
◆子犬におすすめ!トイレのしつけが出来る ドッグルームサークル(床つき)

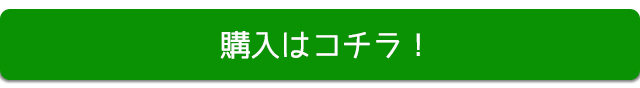
トイレの寝床が分かれている室内サークルで、子犬のしつけが行いやすいのがメリットです。
◆サイズ調整可能!フリップオーバーサークル
1つのサークルで2倍の広さに調整できる万能室内サークルで、愛犬の成長に合わせてサイズ調整することができます。
愛犬をサークルに慣らそう!
子犬であっても成犬であっても、サークルに初めて入るときは怖がることが多々あります。
サークルに慣れていない犬にとって、基本的にサークル内は未知の世界で得体の知れないものです。
まずは、サークルに良いイメージを植え付けるためにおやつを入れて犬を誘導させ、サークルに入ったタイミングで「ハウス」などのコマンドを発してから十分褒めましょう。
はじめはサークルから犬が出てきても問題ないので、ドアを閉めずに同じことを繰り返します。
犬が十分サークルに慣れてから、ドアを閉めるトレーニングを行いましょう。
ドアを閉める場合は、最初はほんの数秒から慣らし、少しずつ時間をかけてドアの閉まっている時間を延ばしていきましょう。
室内犬用サークルに関するまとめ
犬の室内サークルについて必要性・メリットや設置位置など幅広くご紹介致しましたが、サークルは上手に利用することで愛犬の快適な生活をサポートしてくれます。
愛犬にとって安心できる自分だけのテリトリーを作り良質な睡眠をサポートすることで、肉体的・精神的な健康維持のために是非活用してみてください。
– おすすめ記事 –
| ・犬を飼いたいと思ったら考えてほしい、犬を飼える人の条件や心構え一覧。初期費用や年間支出は? |
| ・犬のおやつに「にぼし」はOK?メリットや注意点はある? |
| ・なぜ犬は赤ちゃんを守ろうとするの?赤ちゃんと犬の触れ合いの注意点 |
| ・犬はお留守番の時、何をしている?犬を留守番させるときの注意点 |












