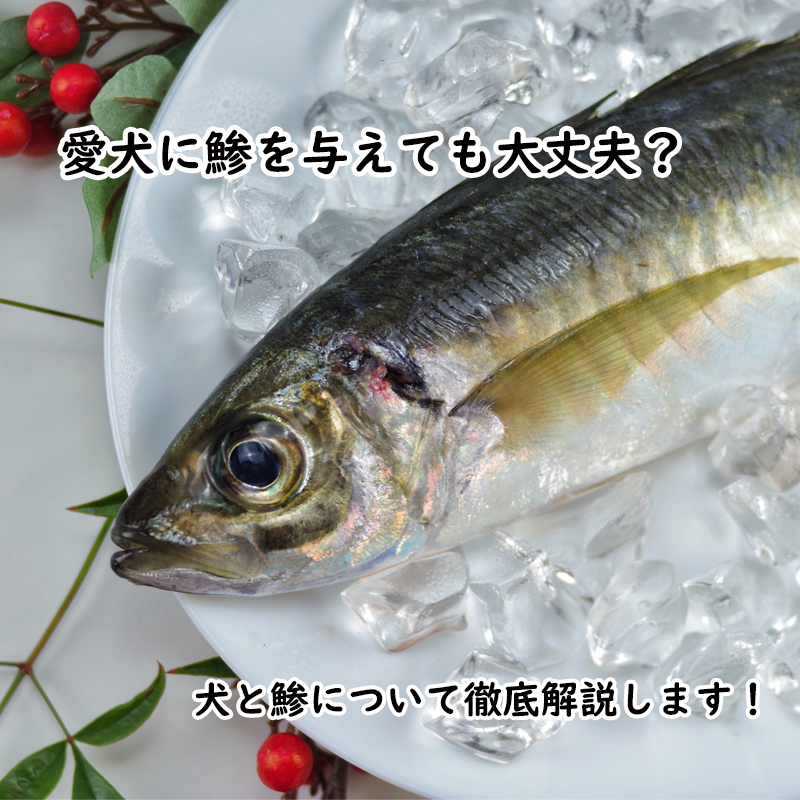1.犬にびわを与えてもいいのか
1-1.与えてもいい
1-2.効果
2.びわに含まれる栄養素
2-1.β‐カロテン
2-2.β‐クリプトキサンチン
2-3.クロロゲン酸
2-4.ビタミンC
2-5.カリウム
4.犬にびわを与える際に注意すること
4-1.種や葉を与えない
4-2.アレルギー
4-3.新鮮なびわを与える
4-4.びわの加工食品
犬にびわを与えてもいいのか

はじめに、犬にびわを与えてもいいかについて、確認しておきましょう。
◆与えてもいい
結論から言えば、犬にびわを与えても大丈夫です。犬の味覚は、甘味を強く感じます。このため、びわの甘さを好む子も多いと思われます。
ただし、与えていいのは実の部分(果肉)だけで、種子や葉は犬にとって毒性を持つ成分を含むので、絶対に与えてはいけません。この点については、後述します。
◆効果
びわは、リンゴやイチゴ、モモ、サクランボなどと同じくバラ科の植物です。
「大薬王樹」(だいやくおうじゅ)と呼ばれるほど様々な薬効を持つことで知られる葉は、古くから漢方に取り入れられてきました。記録によると、聖武天皇の皇后・光明皇后が創設した治療院で、びわの葉療法が採用されていたそうです。
犬にとっても、実を食べることは、ある程度の健康効果を期待することができると考えられます。
皮膚や粘膜の健康
びわは、β-カロテンやβ‐クリプトキサンチンが豊富な果物です。
犬がこれらの栄養素を摂取すると、体内の酵素の働きで必要に応じてビタミンAに変換されます。物を見るときには、網膜の細胞に含まれるロドプシンという物質が必要で、ビタミンAがロドプシンになります。
ビタミンAには、他にも、皮膚細胞の成長を助ける、皮脂の分泌量を調節する役割があります。また、皮膚のターンオーバー(入れ替わり)のために大切な栄養素で、亜鉛やアミノ酸などと一緒に働きます。皮膚や粘膜の免疫や抵抗力を高め、感染症を予防する効果、被毛をきれいに保つ効果も期待できます。
β-カロテンをはじめとするカロテノイドは、抗酸化作用を持つことで知られており、体内の活性酸素を抑え、酸化(老化)を防ぐ効果も期待されます。
クロロゲン酸の抗酸化作用
クロロゲン酸はポリフェノールの一種で、ポリフェノールは細胞膜やDNAを保護する役割を持っています。また、ポリフェノールは、発がん予防物質としても期待される成分です。
さらに、酸化によって体にかかるストレスを軽減する効果もあり、シニア期に差し掛かる犬や病気を抱える子など酸化ストレスが大きい子は、抗酸化成分を摂っておいて損はないでしょう。
また、癌の発症を抑える効果があると言われ、注目を集めています。
コーヒーに入っている成分としても有名で、脂肪の燃焼効果や蓄積を抑える効果があり、肥満の予防や改善の効果も期待できます。
脱水予防
みずみずしい果実の約90%が、水分です。
旬である5~6月は、気温がだんだん上がり始めて、必要な水分も増えてきます。
シニア犬など脱水が心配な子の飼い主さんは、びわを水分摂取のきっかけづくりに利用してもいいでしょう。少し潰した果肉を水と混ぜたものをあげたり、少なめに水を入れたお皿に果肉を切ったものを入れてみたりして、水を飲むきっかけにしてみましょう。
カリウムのデトックス効果
カリウムは、水分と同時に摂取することで、体内の余分な塩分や老廃物をスムーズに排出する効果(デトックス効果)が期待できます。
また、血圧を正常に整える効果もあります。
ビタミンCによる免疫強化
ビタミンCは血液中の白血球、特に好中球に多く含まれ、体外から侵入した細菌やウイルスなどを撃退する役割を担っており、免疫を強化して感染症を予防したり、回復を早めたりする効果があると言われています。
びわに含まれる栄養素
ここでは、びわに含まれる栄養素をご紹介します。
※含有量は、文部科学省の食品成分データベースに基づく生の実の可食部100g当たりの数値です。
◆β‐カロテン
カロテノイドの一種であるβ‐カロテンは、黄色やオレンジの色素成分で、510μg含まれています。
◆β‐クリプトキサンチン
β‐クリプトキサンチンは、600μg含まれています。
◆クロロゲン酸
クロロゲン酸の含有量は微量ですが、前述の通り、抗酸化作用を持つポリフェノールです。
◆ビタミンC
ビタミンCは、5mg含まれています。
◆カリウム
カリウムは豊富で、含有量は160mgです。
びわの与え方
犬が食べてもよいびわですが、どのように与えればよいでしょうか?
◆量
びわを好む犬も多く、健康効果も期待できますが、一度に大量に与えるのはNGです。与えすぎると、消化不良から下痢や嘔吐などを引き起こす可能性があります。
あくまで、おやつ程度に与えるようにしましょう。おやつや間食は、1日の食事量の10%程度を目安とします。
超小型犬(4kg未満)
超小型犬は、1日の食事量が100~250g未満ほどです。
したがって、与えていい量は10~25g程度となります。果実1個当たりの可食部分は平均32gなので、目安は1/3個ないし1/2個ほどです。
小型犬(10kg以下)
体重5~10kgの小型犬の1日の食事量は、300~500gほどです。
したがって、与えてよい量は30~50g程度となります。1個~1個半程度が、目安です。
中型犬(25kg以下)
中型犬の定義には幅がありますが、ここでは25kg以下の犬について適量をご紹介します。
1日の食事量は、体重により500~1000gの間となります。
したがって、与えていい量は50~100gとなり、およそ1個半~3個程度が適量の目安です。
大型犬(25kg以上)
25~40kgの大型犬では、1日の食事量が1000~1450gほどなので、与えていい量は100~145gとなります。目安は、3個~4個程度です。
子犬
消化器官が未発達な子犬の場合、特に注意が必要です。
肉食寄りの雑食動物である犬は野菜や果物の消化能力が低いので、消化器官が未発達な子犬がびわを食べると、胃腸に負担がかかります。胃腸の負担は下痢や嘔吐を引き起こす可能性があるため、絶対に与えてはいけないわけではありませんが、与えない方がよいでしょう。
◆皮を剥いて小さく切る
皮は、消化に良くありません。また、農薬が残量している可能性もあります。
必ず、皮を剝いて与えましょう。
また、後述しますが、種を食べてしまうと体内で毒性のある物質に変化するので、種は取り除いてください。
皮と種を取り除いた果肉部分を、小さく切って与えましょう。フードプロセッサーなどで砕くと、より消化しやすくなります。
犬にびわを与える際に注意すること

◆種や葉を与えない
与える際には、必ず種を取り除いて果肉だけを与えてください。また、葉も与えてはいけません。葉を煎じたびわ茶も、与えないでください。
種や葉には、「アミグダリン」と呼ばれる成分が含まれています。アミグダリンそのものに毒性はありませんが、体内で酵素により分解されると「シアン化水素」に変化します。シアン化水素は、青酸中毒を引き起こす物質です。
人間でも大量に摂取すると、下痢や嘔吐を引き起こし、ひどい場合には昏睡状態に陥る恐れもあります。犬は人間より体が小さく、より危険な状態につながる可能性があるため、種と葉は決して与えてはいけません。
また、アミグダリンは未熟な実にも含まれているため、熟した果実を与えるようにしましょう。
種を与えると、丸呑みして消化管に詰まるリスクもあり、危険です。
◆アレルギー
どんな食べ物もアレルギーの原因物質(アレルゲン)となる可能性があり、びわも例外ではありません。初めて与える場合には、ごく少量にとどめ、食べた後の愛犬の様子を注意深く見守りましょう。
さらに、花粉などの環境アレルゲンに過敏に反応する子は、果物でアレルギー反応を引き起こすことがあります(交差反応)。これは、原因となるアレルゲンの構造が似ているためです。
特にバラ科の果物で出る事が多く、シラカバやハンノキなどカバノキ科のアレルギーを持っている愛犬は、注意してあげましょう。
◆新鮮なびわを与える
びわは、ちょっとした衝撃によって表面が傷つきやすく、傷みやすい果物です。取り扱いの際には、爪を立てたり落としたりしないように注意しましょう。
傷んだ食べ物は消化に悪く、愛犬の胃腸に負担がかかるので、新鮮なものを選び、早く食べきることが大切です。
新鮮なものを見分けるには、以下のポイントをチェックしてみましょう。
・へたがしっかりしている
・表面に張りがあり、形崩れしていない卵形である
・色ムラがなく、全体に黄橙色である
また、表面に産毛がついていれば新鮮な証拠です。
びわは暖地で育つため、冷蔵庫で長時間保存して低温になると、傷みを促進する原因となります。冷暗所で保管して、2日以内に食べきりましょう。
◆びわの加工食品
加工食品として、コンポートやジャムなどが販売されていますが、これらを犬に与えてはいけません。
コンポートは甘いシロップで煮たものであり、市販のジャムにも砂糖や香料が含まれているでしょう。
糖分や添加物は、犬の健康を害する恐れがあり、肥満や糖尿病につながる可能性があります。
まとめ
初夏の味覚びわは、葉が古くから漢方に使用されており、実を食べることで犬にも健康効果を期待することができます。
特にカロテノイド類のβ‐カロテンやβ‐クリプトキサンチンが豊富で、抗酸化作用による老化防止などの効果があると考えられます。また、瑞々しさの元である水分と豊富に含まれるカリウムによるデトックス効果も期待されます。
しかし、種子や葉に含まれるアミグダリンは、体内で毒性のあるシアン化水素に変化するため、決して与えないようにしてください。また熟していない実もアミグダリンを含むので、完熟した新鮮な実の果肉を与えるようにしましょう。
葉をお灸として活用することもできますが、必ず正しい知識のもと、安全に施術してあげてください。
瑞々しく、甘いびわを好むワンちゃんも少なくないでしょう。適量のお裾分けで、初夏の味覚を一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか?
– おすすめ記事 –
| ・犬にスイカをあげるのはアリ?ナシ?愛犬に食べさせたい夏野菜・果物をご紹介 |
| ・犬にも食物繊維は必要?期待できる効果や注意点は?? |
| ・犬が好きな食べ物を紹介!与え方は? |
| ・人気のフルーツ、キウイ!愛犬と一緒に食べられる? |