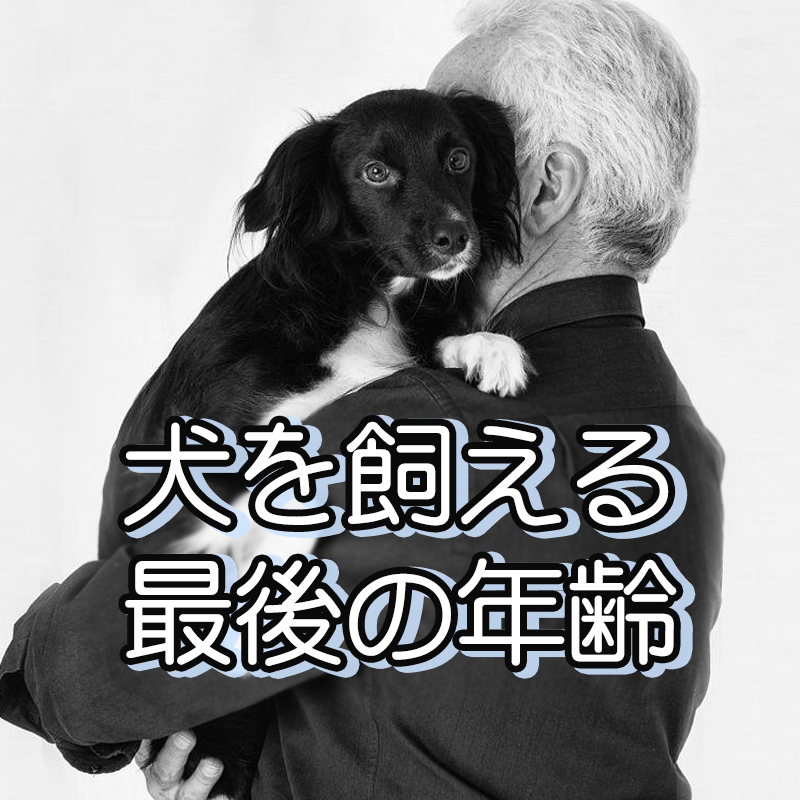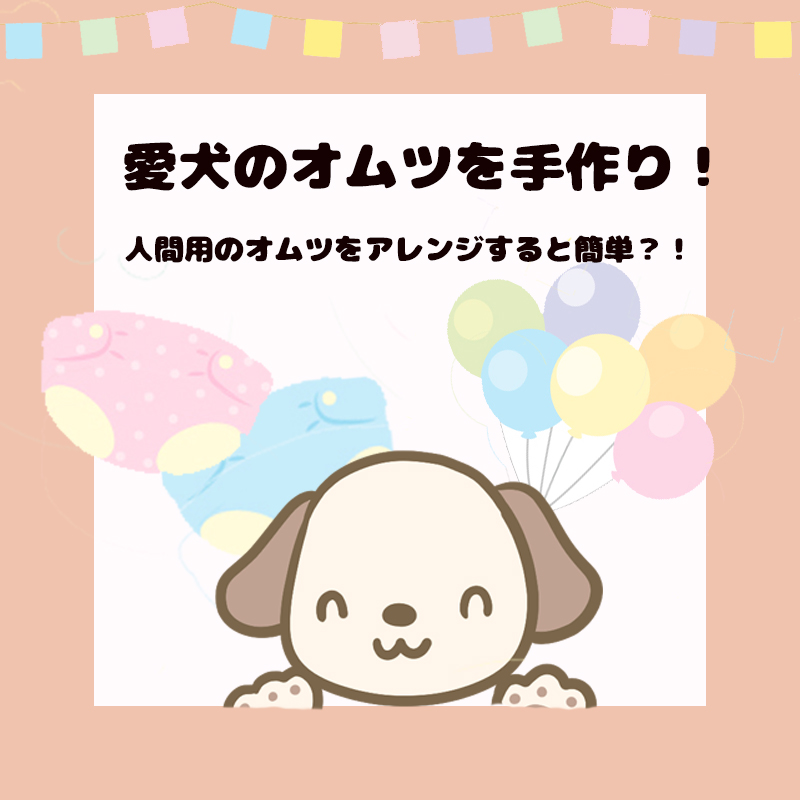【掲載:2022.06.05 更新:2026.02.04】
定年後に犬を迎え入れたい

仕事の引退や定年を迎えて家にいる時間が増えた、余生を愛犬を迎えて共に暮らしたい。このような思いから、定年後に犬を飼いたいと考えている方が現代では珍しくありません。実際にそういった理由から、高齢者となってから犬を飼い始めた方もいるでしょう。
犬を飼い始める年齢に決まりや条件はありませんが、様々な注意点や、前もって考えておくべきことが多々あります。
飼い主さんと愛犬が一緒に長生きでき、幸せな最期を迎えられれば言うことはありませんが、年齢を重ねて犬を飼うこということには、やはり様々なリスクが付きまといます。
それでも犬の飼育を検討したい場合は、まず予想される問題を整理していくことが大切なのです。
まずは犬の寿命を把握し、数十年を共に暮らしていけるか想像してみましょう。
◆犬と人の平均寿命から計算をする
犬の平均寿命は近年上昇傾向にあるといわれており、一般的な犬の平均年齢は14.0歳となっています。
そして日本人の平均寿命はというと、男性が81.41歳、女性が87.45歳と、厚生労働省が2020年に発表しています。
ちなみに、健康上の問題で日常生活に影響がない年齢(健康寿命)についても調査されており、これにいたっては男性が72.7歳、女性が75.4歳だそうです。
このようなデータから、愛犬のお世話を自分で最期まで行うためには、犬を迎える時期は60代くらいまでが適切だと考えられるでしょう。60代でも飼い主さんが置かれた環境や状況によっては、難しい場合もあります。70代での飼育開始は、かなり厳しいといえると思います。
あくまでデータ上の話なのでこれに限ったわけではありませんし、近くに子どもや家族がおり協力してもらえる場合には当てはまりません。ただし、「目安の年代は60代」ということを頭に入れておくべきでしょう。
◆できるだけ若いうちに
犬を飼える最後の年代としての目安は60代ですが、やはりできるだけ若いうちに飼い始める方がリスクは低いといえます。
犬の飼育には日々を過ごすためのお世話はもちろんですが、しつけを行ってルールを教え社会化を図ることや、十分な運動をさせてストレスを感じさせないことも必要なのです。病気や怪我で動物病院への通院が必要となる場合もあります。
問題行動を起こすようになれば周囲に迷惑をかけ、病弱な個体であれば心配が絶えません。犬の性格によっては、飼い主さんが大きく翻弄される可能性も考えられるでしょう。
それまでの生活に変化が伴いますので、犬を飼うことには覚悟が必要なのです。
飼い犬を手放す飼い主さんには様々な事情がありますが、その中には加齢によってお世話ができなくなった、という理由も含まれます。このような残念な結果を生みださないためにも、少しでもリスクを減らすために、できるだけ若い内に犬を飼い始めることがすすめられます。
老後に犬を飼う前に確認しておくこと
定年を迎えてから犬を飼おうと考えている方は、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
年齢を重ねることで起こる障害や身体の不調には、解決策がない場合も少なくありません。
穏やかな毎日を愛犬と共に送るためにも、事前準備を怠らず、あらゆるリスクを想定しておくことが大切です。
◆最期まで世話をできるか
犬も人も年齢を重ねる度に、身体が思うように動かなくなります。日常生活を送る上でも、負担が増えることが予想されるでしょう。
犬を飼う最後の年齢を考える時に重要なのは、数年後・数十年後になっても面倒を見られるかどうかを考慮することです。
飼い主である自分自身の体力が落ちてしまうと、愛犬のお世話ができなくなるかもしれません。
愛犬にとって飼い主さんはかけがえのないパートナーとなりますし、最後まで幸せに暮らしたいという思いもあります。そばにお世話を手伝ってくれる家族や友人がいるかどうか、飼ってからの数十年、愛犬を幸せにしてあげられるかどうかを、事前にしっかり考えてみましょう。
年齢が若いからといって犬を最後まで飼うことを確約できるわけではありませんが、年齢を重ねている分、そのリスクが高いということを理解しておいてください。
◆犬と生活をする体力があるか
犬のお世話をする上で、欠かせないことの一つが散歩です。犬種にもよりますが、大体毎日1回以上の散歩が必要となるのです。
大型犬や活発で長時間の散歩を要する犬種の場合、将来的に飼い主さんの体力が追い付かない可能性が考えられるでしょう。
1回あたりの適切な散歩時間や運動量には違いがありますので、体力に不安を感じる方は、運動量が少なめの犬種を選ぶことがすすめられます。
ちなみに散歩量が少なめの犬種としては、ペキニーズ・狆・チワワ・シーズー・マルチーズ・ポメラニアンなどが挙げられます。
◆経済的な余裕があるか
犬との生活を始めるためにかかるのは、生体費用だけではありません。お世話をするためのグッズや、ワクチン・動物病院にかかる費用、ペットフードやおやつなどの食事代、トリミングやドッグランなどの施設の利用費など、さまざまな経費が必要となります。
犬種・飼い方によって差は出るものの、年間20~30万円程度はかかると考えておきましょう。
事前に毎月の収支を確認しておき、問題なく犬との生活が送れるかどうかを計算してみてください。
ちなみに大型犬の方が飼育費用が掛かります。
さらに、トリミングが必要な犬種かどうかといった点も、必要経費に大きく影響するでしょう。トリミングが必要な犬として代表的な犬種は、トイプードル・ヨークシャーテリア・シーズー・マルチーズ・ミニチュアシュナウザーなどです。反対に、柴犬・パグ・チワワ・フレンチブルドッグなどは、トリミングを必要としない犬種として挙げられます。
◆サポートしてくれる身近な人がいるか
愛犬は人生を豊かにしてくれる存在となりえますが、お世話は簡単だとはいえません。
歳をとると、体力の低下や運動面での障害を感じることも多くなります。例えば毎日の散歩が困難となったり、動物病院への通院が大変になるなどの問題に直面する可能性が考えられるのです。飼い主さん自身が体調を崩したり、入院が必要となる場合もあるでしょう。
そんな時のためにも、身近に犬を飼うことをサポートしてくれる方がいるかを確認しておくことが必要なのです。
周囲に仲の良い友人がいたり、家族が近隣に住んでいるのであれば、事前に相談してみてください。
◆万が一自分が亡くなった後に誰が犬を引きとるか
老後・定年後に犬を飼う場合、飼い主さんが先に亡くなってしまうケースも実際に少なくありません。
できれば避けたい事態ですが、自分の後を継いで愛犬を引き取り、愛情をもって世話をしてくれる誰かを決めておく必要があるのです。
もしも家族や親戚に犬を飼える方がおり、関係性も良好なのであれば、その家族にお願いするのが一番良いでしょう。
そのような方がいない場合は、仲の良い知り合いや友人に、里親になれる方がいないか確認しておくことをおすすめします。
犬を飼う前に引き取り先を決めておくことができれば、老後や定年後にも安心して犬を飼い始めることができます。
犬を迎え入れることは、その子の命に責任をもつことです。最後まで人生を共にできることが望まれますが、自分にもしものことがあっても愛犬が幸せに暮らしていけるように、事前準備をしておくことが重要なのです。
60代で犬を飼うリスク
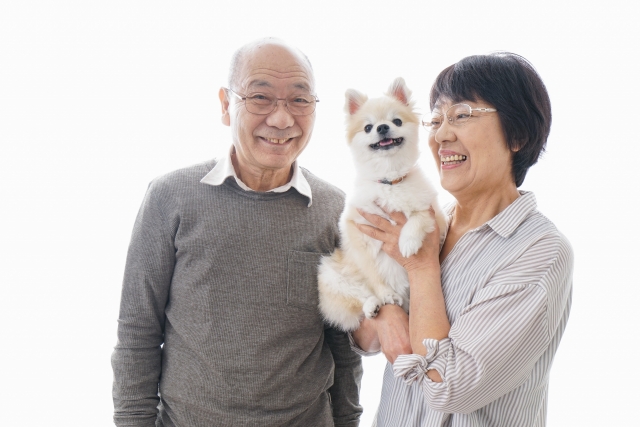
60代を迎えてから犬を飼う場合、考えられるリスクについて予め知っておく必要があります。
まず犬を飼うための方法ですが、ペットショップやブリーダーから購入したり、動物愛護団体・保護団体などから里親として譲渡してもらう方法が一般的です。保護犬を一時期的に預かって育てるという、ボランティア活動もありますね。
しかしここで頭に入れておきたいのが、保護犬の場合は飼い主さんの年齢が問題視され、審査に通らないケースがあるということです。定年後に里親募集で犬を迎え入れようとしても、保護団体から断られてしまう場合が実際にあるのです。
年齢だけが問題ではなく歳を重ねたことがブレーキとなり、その後の不安を大きく感じることから保護団体としても犬を思うからこそ敬遠してしまうのでしょう。
保護団体から保護犬を譲り受けるつもりがない場合においても、犬を飼い始める際の飼い主さんの年齢によって抱えるリスクがあるのは同じです。
どうしても犬を飼いたいと考えているのであれば、特に以下の注意点をリスクとして捉えしっかり受け止めてください。
◆体の大きい犬
お伝えしてきた通り、犬を飼うことが可能だといわれる最後の年齢になると、飼う犬の寿命を気にしなくてはいけません。
大型犬は小型犬よりも平均寿命が短いので、定年後に飼う犬種として向いているのかなと思われる方もいるかもしれません。しかしやはり飼い主さんの年齢の高さに比例して、大型犬を飼うリスクは高くなるといえるでしょう。
大型犬には小型犬と比べて運動量が求められますし、介護が必要となった場合にその体格や体重からも難易度があがります。子犬の内は小さくても成長速度は速く、大きくなるにつれて力も強くなるのです。
60代を迎えた飼い主さんが飼い始める犬としては、難しい種類だと思っておきましょう。
◆抜け毛が多い犬
抜け毛の多さも、犬のお世話のしやすさに大きく関わってくる問題です。掃除の手間はもちろん、トリミングを要する場合には費用も必要以上に掛かります。事前に飼いたい犬種の被毛のタイプについても、情報を仕入れておく必要があるでしょう。
また、抜け毛が少なくともトリミングが必要な犬種もいるので注意してください。
ちなみに抜け毛が少ない犬種としては、トイプードル・ヨークシャーテリア・ビションフリーゼ・マルチーズ・ミニチュアシュナウザーなどが挙げられます。
◆犬の介護が老々介護になる可能性
人間社会でも問題となっている老々介護。これは犬と飼い主さんの関係性としても、目を背けられない問題です。
前述したように、犬も人同様シニア世代に入ると介護が必要となる可能性があるのです。認知症を発症するケースも珍しくありません。犬の介護が始まると、愛犬を抱きかかえることも多くなり、力も体力も必要です。病院への通院も重労働となるでしょう。
愛犬が最後まで健康で元気にいられるよう食事などに気を付けることも大切ですが、万が一に備えておくことも重要なのです。
犬を飼う前に、身近にサポートをしてくれる人がいるかを考えてみましょう。老々介護とならないためにも、助けとなってくれる家族や友人に事前に相談しておく必要があります。
まとめ
犬を飼い始める最後の年齢の目安は60代です。これは明確な回答ではありませんし、飼い主さんの周囲の状況や健康状態によっても差は出ます。
しかし目安として考え、愛犬に不幸な想いをさせずに済むか、併せて飼い主さん自身が幸せに暮らせるかを、しっかり考えてみてください。
犬の飼育は命を育てるということです。
決して安易な気持ちから犬を飼おうとは思わないでください。
万が一を想定してきちんと準備をし、家族や友人に頼れるのであれば事前に相談してみましょう。
– おすすめ記事 –
| ・トイプードルの赤ちゃんの飼い方やしつけ方法は?子犬を迎えるために何を準備する? |
| ・キャンベルテストで子犬の性格診断テスト!犬を迎える前に性格・性質を知ろう |
| ・犬アレルギーを起こしにくい犬種はいる?対策法はある? |
| ・犬の介護に疲れ、辛い人へ。少しでも介護が楽になる改善策 |