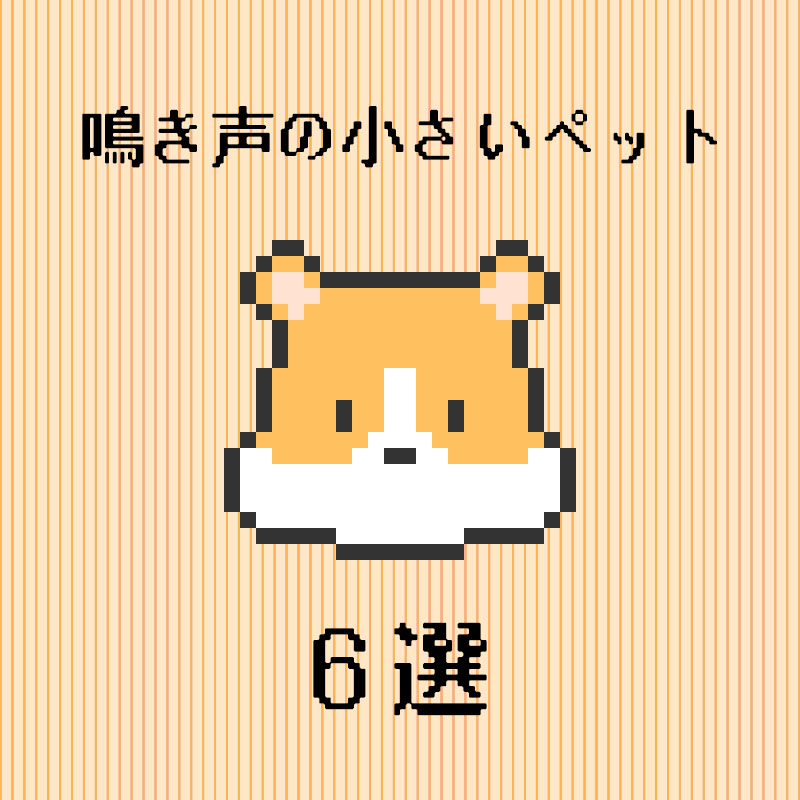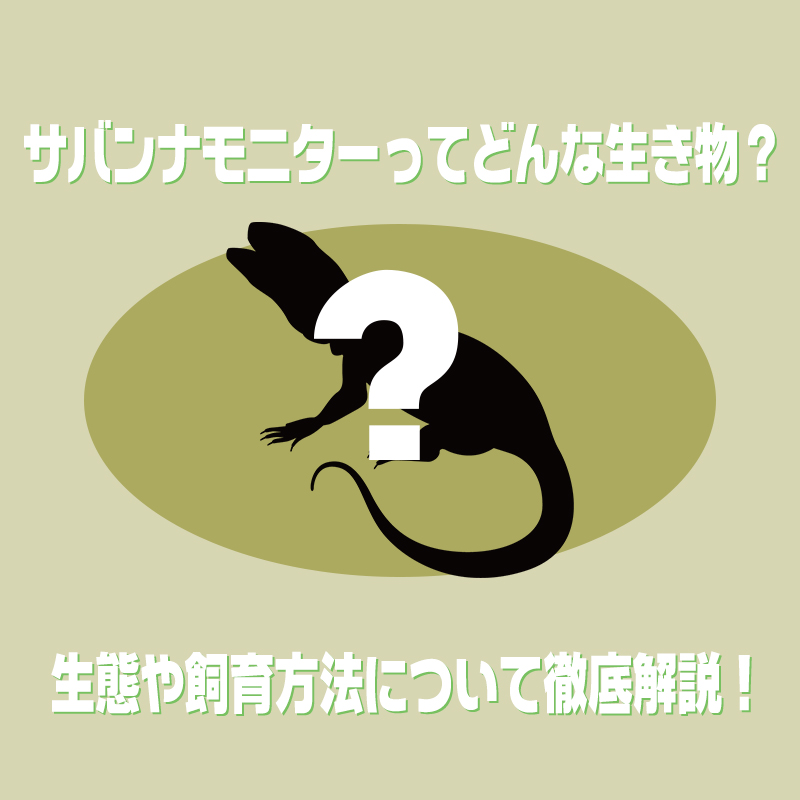あまり鳴かない、鳴き声が小さい小動物6選
早速おすすめのあまり鳴かないペットについて紹介します。
鳴かないと言っても、全く鳴かないわけではなく小さな鳴き声やほとんど鳴かないペットも含めて紹介いたします。
ご自身の家庭環境にあわせて、お迎えするかどうか検討してください。
◆ハムスター

犬や猫に比べて小動物は鳴き声も小さく、飼育スペースも省スペースで良いため、賃貸などの限られたスペースでも飼育しやすいです。
ハムスターはネズミの仲間であり、昔からペットとして人気があり、品種改良されてきました。
大きなサイズのゴールデンハムスターでも、20センチ前後にしか成長しないので、手のひらサイズに収まることが多いです。
ペットとして人気の高いジャンガリアンハムスターは10センチ前後に成長します。
鳴き声はキュキュキュ、プスプス、チューなど小さな声で鳴くことがありますが、めったに鳴かない生き物になります。
鳴き声や声の高さは飼育環境や鳴き声をあげている原因にもより、異なります。
ハムスターが急に鳴いていると飼い主さんは怪我でもしたのかな?とびっくりしてしまうかもしれません。
まずはハムスターが鳴いている原因を特定してあげるのが、大切になります。
ハムスターはビックリするとギュッ!!とワントーン高めの大きめの鳴き声をあげることがあります。
滅多に鳴かないハムスターが大きく鳴く時はストレスがかかっている状態です。
あまりびっくりさせないように注意して、飼育すれば鳴き声はほとんどに気になりません。
鳴き方や頻度については、個体差があるためできるだけ伸び伸びとした静かな環境で飼育しましょう。
ハムスターの飼育に関して注意したい点は、ハムスターは夜行性であり、普段人が寝ている時間に活動します。
回し車で夜中にカラカラと運動することになるため、壁の薄い賃貸などで飼育する時には回し車などの生活音に注意が必要です。
◆うさぎ

うさぎには声帯がないため、鳴き声を出すことがありません。
しかし、機嫌が悪かったりなにか訴えているときには、ブッブーなどと鼻を鳴らすことはあります。
響く鳴き声ではないため、騒音などを機にする必要はありませんが、うさぎが何か主張があることが多いので、原因を特定して聞いてあげるようにしましょう。
稀に高い声でキーっと鳴くことがありますが、この鳴き声はうさぎにとって痛い!!という訴えの時が多いため、緊急性の高い鳴き声になります。
どこか挟んでいないか、怪我をしていないか、異常がないか素早く確認する必要があります。
怪我をしていたり、いつもと違った様子があれば早めに動物病院にて診察を受けるようにしましょう。
普段は物静かでめったに鳴かないウサギは、ペット可の賃貸でも飼育できますよ。
ただし、走り回る音や足をダン!と鳴らすスタンピングという行動の音が響く可能性がありますので、相応の対策は必要です。
◆ハリネズミ

丸いつぶらな瞳と独特の針の毛が特徴のハリネズミは、ペットとして最近人気のある生き物です。
幼少期から育てることにより、人を警戒しなくなるため抱っこされてもおとなしくしていたり、飼い主さんのでの中でたまに寝てしまうなど可愛い一面を見せてくれます。
そんなハリネズミも鳴くことが少なく、鳴いたとしても小さな声で鳴くため、あまり響きません。
ハリネズミの鳴き声は小鳥のさえずりにも似ており、ピピピっやピィーと鳴く姿を見ることができます。
この鳴き声を出している時は、比較的機嫌が良くリラックスしている時に上記のような声を出すことがあります。
安心してお腹がいっぱいの時にもこのように鳴くことがありますよ。
注意したいのは、ハリネズミはペットとしての歴史がまだ浅いため、飼育環境の作り方や日々のお世話などをよくリサーチして、計画的にお迎えする必要があります。
◆フェレット

フェレットはウサギやハムスターに比べるとやや鳴く回数が多いです。
フェレットは感情表現豊かであり、鳴き声により感情表現することがあります。
鳴き声自体は響く声ではないので、犬や猫のようにそこまで気になりません。
また、ぐぅぅぅやシャーっと威嚇や機嫌が悪い時にはこのような声で鳴くことがあります。
スンスンと寝息をもらす可愛らしいところもあるため、ペットとしてもフェレットはおすすめですよ。
◆カメやトカゲ

基本的に亀などは声帯がないため、鳴くことはありません。
稀にクゥーやキューと言った空気の音が聞こえることがありますが、まずカメやトカゲを飼育していて騒音トラブルになることはないため、鳴かないペットをお探しの方は、お迎えを検討するのも良いでしょう。
注意したいのは、カメやトカゲは脱走などしないように飼育ケースに蓋をするなど対策が必要です。
また、カメたちは変温動物のため外気温により体温が左右されます。
爬虫類の飼育には、必ずバスキングライトを準備してカメやトカゲが身体を温められるようにしましょう。
◆金魚などの観賞魚

アクアリウムは自由度も高く、小さな魚を選べば省スペースでペットをお迎えすることができる点が魅力的です。
特に金魚などは丈夫で初めてペットを飼う方にも飼育しやすいため、導入しやすい生き物です。
魚は鳴くことはないため、鳴き声による騒音などを心配する必要はありませんが、ろ過装置のモーター音などが気になる場合があります。
特に古代魚など大きくなる魚を飼育する場合、水槽のサイズやろ過装置も大きなものが必要になってきます。
ろ過装置はモーター音が気にならないような消音タイプのものを選びましょう。
逆によく鳴く、鳴き声が大きい小動物はいる?
鳴き声を気にしているのならば、次に紹介するペットは不向きかもしれません。
騒音対策をして近所迷惑にならないように気をつけてください。
◆インコなどの鳥類
インコなどはさえずりを楽しむために飼育する面もあるため、ちゅんちゅんやピィーピィーなどよく鳴きます。
インコが飼い主さんを呼ぶ時はピー!ピィピィ!など高い声でなくことが多いです。
この呼び声は「70デシベル」と言われており、やかんの沸騰音や掃除機の音と同等の大きさであると言われています。
近所に響き渡る鳴き声ではありませんが、賃貸は隣の部屋まで聞こえる可能性もあります。
インコよりも大型のオウムなどは、もっと大きな声で鳴くためさらに響く鳴き声をします。
鳴き声を気にしているけど、ペットを飼いたいと考えている方はインコなどな鳥類の飼育はよく検討する必要があります。
◆モモンガ
意外に感じる方もいるかもしれませんが、モモンガは鳴き声により多彩なコミュニケーションをとる生き物です。
アンアン、やワンワンというように大きめの声で鳴いているときには、飼い主さんを呼んだり甘えたいという意思表示になります。
また、お迎えしたばかりのモモンガは環境にまだ慣れていないため、シャーやクワっと言った声で威嚇することがあります。
鳴くことが多いモモンガは夜行性ですので、合わせて夜に活動音が気になるという点もあります。
モモンガはきちんと防音対策してからお迎えしたいペットです。
◆モルモット
モルモットは声量はそれほど大きくはありませんが、キュキュキュ、ピィピィなど多彩な鳴き声をあげます。
おしゃべり上手であり、よく鳴くため鳴き声を気にしている方のペットには向きません。
ケージをガジャガシャしたり、元気に走ったりと意外にも活動的な面もあるため、動きにより音が発することがよくあります。
どんなペットでも飼うときは周囲への配慮が必須!
鳴き声が気にならないペットや逆に要注意なペットを紹介してきましたが、ペットを、飼う時には周囲への配慮がもちろん必要です。
ポイントを紹介します。
◆必ずペット可物件で
賃貸の場合は必ずペット可の物件で飼育しましょう。
ペットの飼育には責任が伴います。
終生飼育するためには、必ずペット可の物件で飼育することが必須です。
ペット不可の賃貸で飼育していたのがバレてしまい、手放さなくてはならないという状況になってはいけません。
ペット可物件であれば、周りも動物好きな人が多く、周りでも飼っているためお互い許容しながら鳴き声について理解してもらえることが多いでしょう。
◆騒音対策は必須
鳴き声が少ないと紹介したペットでも、夜行性で夜に活動したり、ろ過装置のモーター音が気になることがあります。
どんなペットでも生きている以上、無音で生活することは難しいため、飼育スペースを音が響かない部屋にするなど防音は必須になります。
◆共用部分へ出すときはケージへ
仮に何か作業などをするためにペットを共用部分に出さないと行けない時は必ずケージに入れましょう。
放し飼いは逃走の危険や思わぬトラブルの原因にもなります。
ペットの命を守るためにも、ケージに入れましょう。
◆臭いには気を付けて
鳴き声や音と一緒に気をつけたいのが、臭いです。
臭いもトラブルの原因になりやすく、トイレは清潔に保つ必要がありますし、ペットの体臭にも気を付けなければなりません。
定期的に掃除を行い、ペットが快適に暮らせる空間を維持しましょう。
まとめ
ペットの鳴き声について紹介しました。
鳴き声が小さなペットを飼いたいと考えている方は、是非参考にしてください。
また、鳴き声が大きいと紹介したペットでも、防音をしっかりすれば、ペット可の賃貸で飼えるであろうペットです。
どんな生き物でも、飼育するうえで音や臭いの問題は起こります。ペットの鳴き声と上手に付き合っていきましょう。
– おすすめ記事 –
| ・ペットのトカゲは何を食べる?種類別の食性と与える餌や注意点、拒食対策を解説 |
| ・【ペットの亀の冬眠】させたほうがいい?時期や気温は?冬眠のメリットとデメリット |
| ・ペットとして人気のカワウソの値段はいくら?飼育方法は? |
| ・きょとんとした姿が可愛い!ペットとしても人気のフクロウの種類と特徴をご紹介! |